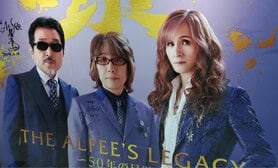「インクルーシブ」「インクルージョン」という言葉を知っていますか? 障害や多様性を排除するのではなく、「共生していく」という意味です。自身も障害のある子どもを持ち、滞在先のハワイでインクルーシブ教育に出合った江利川ちひろさんが、インクルーシブ教育の大切さや日本での課題を伝えます。
* * *
夏休み終盤になりました。私は今、高3の息子の大学受験の出願間際で気持ちが落ち着かない毎日を過ごしています。我が家は年子なので、昨年の次女の大学受験から2年連続で受験生がいる環境です。特に、障害のある息子は学校選びなどでも検討や確認することが増えます。大学受験では保護者は見守ることしかできないのですが、ついつい書類の確認など口出ししたくなってしまいます。不安を挙げるとキリがありませんね。今回は、我が家の子どもたちの大学受験について書いてみようと思います。
空間認知が苦手で漢字に苦労
息子は、脳性まひの影響でひざ下が不自由な軽度肢体不自由児です。幼少期には空間認知が苦手で画数の多い漢字を書くことに苦労したのですが、本人が選んだ進路はなんと、古典文学が学べる学部でした。
私にはまったく知識のない分野で、息子が購入した古文の参考書は文章の意味どころか読めない字もたくさんあります。あんなに字や絵を書くことが苦手だったはずなのにいつの間にか克服していた姿を見ると、親バカながら息子をとても頼もしく思ってしまうのです。
次女は小学生頃から医療従事者になる夢がはっきりしていたので、大学選びは最終的な目標(就職先)から逆算して志望校を決めました。学部が決まっていたため、彼女の偏差値と自宅から通える範囲の大学で検討してすんなり決まったように思います。でも息子は将来の職業に直結する学部ではないため、高2の終盤になっても志望校が決まらずにいました。
そんな中、夫と一緒にオープンキャンパスに訪れたある大学を気に入り、第1志望校が見つかりました。オープンキャンパスでは、通学ルートの確認もします。足が不自由な息子には、手すりがある場所の把握もとても重要です。
この大学は古典文学を専門的に学べるところです。推薦基準も満たしていたため親としてはとても安心したのですが、念のため併願可能な大学も受験することにして、高3になってから説明会に参加すると、2つの大学の受験日が重なる可能性があることが分かりました。確定するのは出願後です。万が一、受験日が重なって第2志望校を辞退した場合は、当然ながら今年度はもう受験することはできません。仕方ないので、まずは第1志望校を専願で受験し、不合格だった場合は再度検討することになりました。