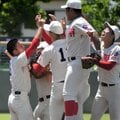春夏連覇を狙った横浜も準々決勝で敗れたが、さすがの力を見せた。チームを牽引したのが、2試合連続完封勝利をあげた織田翔希(2年)だ。チームとしても3回戦までの3試合でわずか1失点と、相手打線に付け入る隙を与えなかった。ただ、もう一人の投手の柱である奥村頼人(3年)が神奈川大会から調子が上がらず、織田への負担が大きくなったことがベスト8で敗退した大きな原因と言えそうだ。
次にベスト8入りを予想しながら勝ち上がることができなかった4チームについて触れたい。
健大高崎と智弁和歌山については先発を任された下重賢慎(3年)と渡辺颯人(3年)が春に比べて状態を落としていたことが誤算だった。ともに地方大会でも登板は少なく、その間に調整してきたとは思われるが、好調時に比べると明らかにストレートの勢いがなく、持ち味の変化球の威力も半減していた印象だ。また智弁和歌山については特に左の技巧派に対して打線が力を発揮できなかったという点も敗因だったと言えるだろう。
神村学園については49番目の登場という点がまず難しい部分だったように見えた。先発した早瀬朔(3年)は鹿児島大会に比べるとかなり状態が上がっていたが、春の九州大会と夏の鹿児島大会で好調だった打線が完全に創成館先発の奥田晴也(3年)の前に沈黙。改めて長期間の調整と、一つ勝ってきたチームと戦うことの難しさを感じた。
最後の明豊については大きな誤算はなかったように見えるが、敗れた県岐阜商戦では相手チームを上回るヒット数を放ち、再三チャンスを作りながらもあと1本が出なかったという印象だった。
最後に、開幕前にベスト8と予想していなかった4チームについて触れたい。
京都国際と東洋大姫路は力のあるチームと考えていたため、それほど驚きはなかった印象だ。また関東第一についても昨年準優勝を経験したメンバーが残っており、どちらかと言えば神村学園が力を発揮できずに早々に敗退したことが大きな要因のように見える。