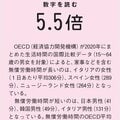小説家・平野啓一郎が新著「あなたが政治について語る時」(岩波書店)を上梓した。
文学・芸術を論じた「文学は何の役に立つのか?」(岩波書店)に続く本作は、政治・社会を論じたエッセイ集。政治への期待感の低下や、政治を語り合うこと自体が避けられがちな現代において、「社会の居心地を良くするためには、政治を通して、ルールや仕組みを変えるしかない」という平野さんの言葉には大きなヒントが含まれている。
平野啓一郎さんの短篇集『富士山』に関するインタビューはこちら
* * *
自己責任論は政治のサボタージュ
――「あなたが政治について語る時」は、政治・社会に対する時事評論をまとめた作品。タイトルに“政治”という言葉を使ったのはどうしてですか?
我々がこの世界に居心地の悪さを感じたときに、何ができるかを考えると、やはりルールや仕組みを変えるしかないと思いますし、それは結局、政治に関わるしかないんですよね。政治は遠いものと感じている方もいらっしゃるでしょうが、自己責任論から脱し、問題を解決するのが政治の本来の役割なので。私自身もいわゆるロスジェネ世代で、「自分たちの責任にされるのはたまったもんじゃない」という思いが根強くあるんです。自己責任論は政治のサボタージュ。責任を個人に押し付けることで、やるべきことをやっていないという批判を避けようとしているんだとしか思えない。政治に対する失望や諦めによって、投票率が上がらなかったり、政治の話をしたくないという雰囲気もありますが、今回の本を通して「政治で自分の状況は変えられる」ということを言いたかったんです。
――「主権者教育なき日本」の章では、日本においては、自分たちの手で社会のルールを作っていく経験が乏しいことを指摘されています。
60年代、70年代の学生運動の取り締まりの影響だと思うんですが、私が中学、高校の頃も学生の自治が許されず、とても厳しく管理されていました。生徒の側から校則を変えることもできず、学級委員や生徒会も学校のガバナンスの一部になっていて。そういう10代を過ごさせておいて、「さあ、投票しろ」と言われても、投票所に行くはずがないですね。
本にも事例として書きましたが、先進的な主権者教育で知られるオランダでは、中高生の代表からなる「全国生徒協議会(LAKS)」という組織があり、教育関連の法律が制定・改正される際には、このLAKSの意見を無視することはできないんです。この組織の運営費用は、全額、教育文化科学省が賄っており、代表者には国会で演説をする機会も与えられている。こうした経験があれば、自治体の在り方にも積極に参加できる。そういうプロセスがまったくない状態で、若者の政治的無関心を嘆くのはとても奇妙だと思います。