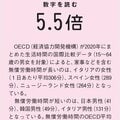政治を語ることへの萎縮 考える力の喪失
――さらに政治の話がしづらい風潮もあります。
それは日本だけではなく、世界的な傾向でしょうね。強権的な政権の影響もあり、「社会的・政治的な発言することが将来の自分にどういう影響をもたらすかわからない」となれば、どうしても萎縮してしまう。ただ、批判は未来のリスクを回避するためのものです。「このまま黙っていると、未来の社会に非常に大きなリスクがある」という時に批判をしないと、将来的に、そのリスクは必ずのしかかってくる。アベノミクスの失敗がいい教訓です。次々にいろんな問題が起きて、しばらくすると忘れてしまうのも大きな問題ですよね。
朝日新聞のインタビューでも言いましたが、今の日本は、考えることに不真面目になっている。「失われた30年」と言われ、あらゆる経済指標が日本の凋落を示していて。それは少子化、産業構造の停滞、DXやAIの遅れなどさまざまな問題が絡み合って起きているわけですが、一つひとつを真面目に考えて解決しようという雰囲気になかなかならない。それどころか、金融緩和さえ進めればいいとか外国人が優遇されているからだなどと、非常に短絡的な思考に陥り、結果的に停滞を長引かせています。
――そういう状況のなか平野さんは、SNSでも社会的な発言を積極的に行っています。
そうした僕の姿勢に対する批判もありますが、たとえばサイン会で「SNSもフォローしてます」と言われることも多いですし、僕の発言に共感して、小説を読んでみたという方もいます。海外の作家と接する機会もありますが、同じように自分の政治的スタンスを表明している人は多いです。まあ、基本的にはリベラルで、海外の文学シンポジウムに参加している作家やアーティストと話をすると、「多様性が大事だ」とか「弱者が搾取される社会は良くない」と、非常に意見は近いのですが、それは文学を読んできた結果ですし、そういう意味では作家同士の連帯感もあると思っています。あとは僕自身も――意識的にそうしたわけではないですが――共感した作家たちは政治に深く関わった人が多かったんです。三島由紀夫、ドストエフスキーもそうですが、社会について深く考えていった結果、政治に行き着いていた。必ずしも彼らの政治的な立場に賛同しているわけではないですが。