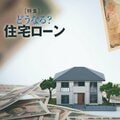みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部・上席主任エコノミストの井上淳氏は次のように解説する。
「足元では消費者物価指数が7カ月連続で3%台という少々高めの水準にありますが、着実に賃上げは進んでいます。トランプ関税の交渉が一段落したことで、景気の腰折れリスクは低下したと見ています。日銀が注目する賃上げについても、国内非製造業が高水準を維持していることを考えると、2026年度も賃上げが続く可能性が高いでしょう。日銀は15%の対米関税が景気に与える影響を見極めたうえで、26年初頭には利上げを再開するとみています」
足元ではドル/円が147円円前後で推移しているが、再び150円を超えて円安が進むようならば、これも輸入物価の上昇を招くため、日銀の利上げムードを高める材料になることも留意しておきたい。
仮に、0.25%相当の利上げを2度実施すれば、26年度中に政策金利は1%へ。おのずと住宅ローンの変動金利もさらに0.5%程度の上昇する可能性が高いという。割安の金利を提示しているネット銀行でも最優遇金利は1%近くに達すると予想される。
同様に、固定金利も上昇は避けられない。固定金利は長期金利に連動する傾向がある。
参院選真っ只中の7月半ば、長期金利(10年国債利回り)が一時1.595%まで上昇した。「約17年ぶりの水準」と報じられたことに、一部の人は肝を冷やしたという。
市場関係者は「政策金利を1%に引き上げる仮定で、さらなる利上げを織り込むかたちで長期金利は2%台に乗せてくるだろう」と話す。おのずと固定金利も現在の1.8%台から2%を超えてくることが予想されている。
さらに長い目で見れば、金利は一層高くなる可能性がある。
前出のみずほリサーチ&テクノロジーズでは2023年11月に「『金利のある世界』への日本経済の適応力」と題したレポートで、「政策金利の到達点を2.75%」とし、変動金利が4%に到達した場合のストレステストをしている。