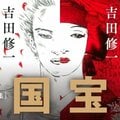「小説に勝ちに来ていると感じた」
映画は歳月だけでなく、喜久雄と俊介の周囲にいる人たちも大きく刈り込む。喜久雄の幼なじみであり、命を張って喜久雄を守ろうとする徳次は、原作の中ではとりわけ人気の高いキャラクターだったが、冒頭に子役として出たきり消えてしまう。脚本の奥寺佐渡子、監督の李相日コンビの大胆な決断は、吉田修一をして「小説に勝ちに来ていると感じた」と言わしめた。
ほかにも、チンピラから売れっ子芸人になる弁天や、喜久雄をいじめる女形の鶴若ら人間味あふれるキャラクターがカットされている。
そして何よりも女性たちである。喜久雄の恋人だった春江(高畑充希)や、喜久雄の子を産む藤駒(見上愛)、喜久雄に利用される彰子(森七菜)らは映画にも登場するが、原作ではもっとしっかり描き込まれている。
喜久雄と俊介に焦点を絞ったため、映画では、女性たちの言動が理解しにくいうらみが残った。原作を読むと、彼女たちの心理が詳しく書かれており、映画を補完する役割を果たすことになる。せっかく芸達者な女優をそろえたのに見せ場が少なめで、ちょっともったいない。映画がここまでヒットしたのだから、再びこの女優たちを集めて、スピンオフ映画「女たちの国宝」を作ってもらいたいと思う。こちらは女性監督がメガホンを取るのはどうだろう。
吉沢亮と横浜流星、二人の男優が素晴らしいことはあちこちで言われており、ここでは繰り返さない。ただ、うるさ型の多い歌舞伎ファンがおおむね好意的だというのは快挙だと思う。誰もが六代目中村歌右衛門を想起する小野川万菊を演じた田中泯に至っては、大絶賛以外の感想が全く聞こえてこないくらいだ。
「読んでから見るか、見てから読むか」という角川春樹の名コピーに倣うならば、私は「見てから、読んでから、もう一度見る」ことをお勧めする。ジェットコースターのだいご味を堪能したうえで、登場人物の深い心理をつかみ、もう一度映画を見ると、細部の感動が違ってくることだろう。映画と原作は別物ではあるが、「国宝」の場合、別物として作られながら、相互作用をもたらしている。