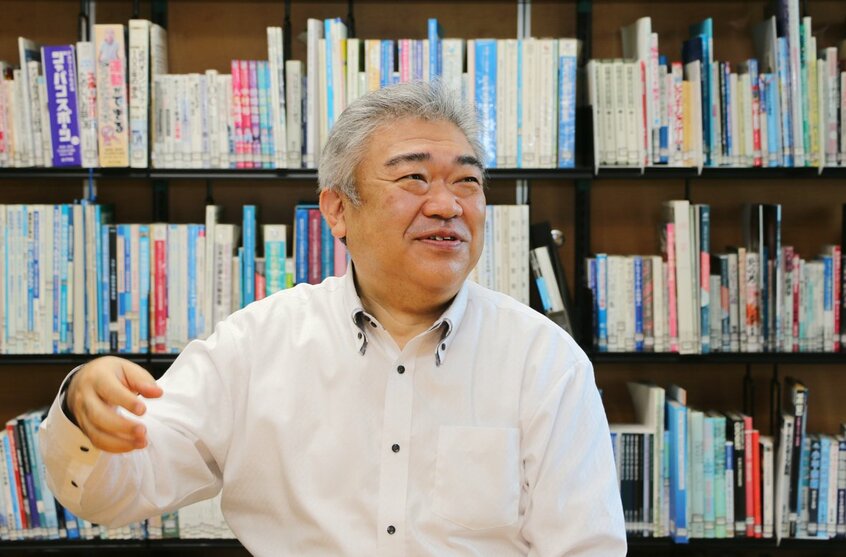
ただし、同市のように、プール授業の本来の目的に立ち返り、授業を工夫する自治体は多くないようだ。中学校のプール授業を廃止したいくつかの自治体に取材したが、老朽化したプールの維持改修費以外の話が出ることはほとんどなかった。
体系的に学ぶプログラムを
学校のプールのあり方について、自治体にアドバイスしてきた笹川スポーツ財団の熊谷哲・上席特別研究員は、こう指摘する。
「『他の自治体が費用のかさむプールの授業をやめたから、うちも』という安易な姿勢が感じられる自治体は、残念ながら少なくありません」
熊谷さんは、自治体から相談を受けるなかで、水難事故防止のためにプール授業の重要性を訴える国の姿勢と、自治体の認識がかみ合っていないことを強く感じてきた。
そして、その大きな原因は学習指導要領にあると見る。着衣泳に関する記述はなく、指導要領解説に、「着衣のまま水に落ちた場合の対応の仕方について」は、「各学校の実態に応じて取り扱うことができる」などと記されているのみだ。そのため、水の事故をなくそうと創意工夫する自治体と、そうでない自治体とのギャップが大きいという。
「水難事故防止が重要なのであれば、授業内容を自治体まかせにせず、体系的に学ぶプログラムを学習指導要領に記すべきでしょう」(熊谷さん、以下同)
民間のスイミングスクールのプールを利用
学校のプールを廃止して、民間のスイミングスクールのプールを利用した実技授業も増えている。水泳の指導は主にインストラクターが行う。教員は学習指導計画づくりや児童・生徒の評価に専念できるので、教員の負担軽減のメリットも大きいという。
たとえば、京都府福知山市では、昨年度から民間の温水プールを利用した水泳の授業が市立小学校ごとに、ほぼ1年を通して行われている。児童や教員の移動には市のスクールバスを活用する。
「天候に左右されず、更衣室も奇麗です。アンケートをとると、83%の児童が『泳ぐことが好きになった』と答えました。保護者や教員からも好評です」
持続可能なプールの仕組み
ただし、スイミングスクールのプールに頼れない地域も少なくない。
「公営・民間の区別なく、住民の健康増進も含めたプール施設のあり方や利活用に工夫を尽くすことが大切です。大切なのは子どもたちが楽しく取り組めるプール授業であること。それを大前提に、持続可能なプール授業の仕組みをつくってほしい」
大人世代が当たり前のように受けてきた水泳の授業が大きく変わりつつある。子どもたちにとって何がベストなのか。建設的な議論を進めてほしい。
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 【早わかり】「部活動」ココがつらいよ 保護者と顧問のホンネ【2分で解説】





































