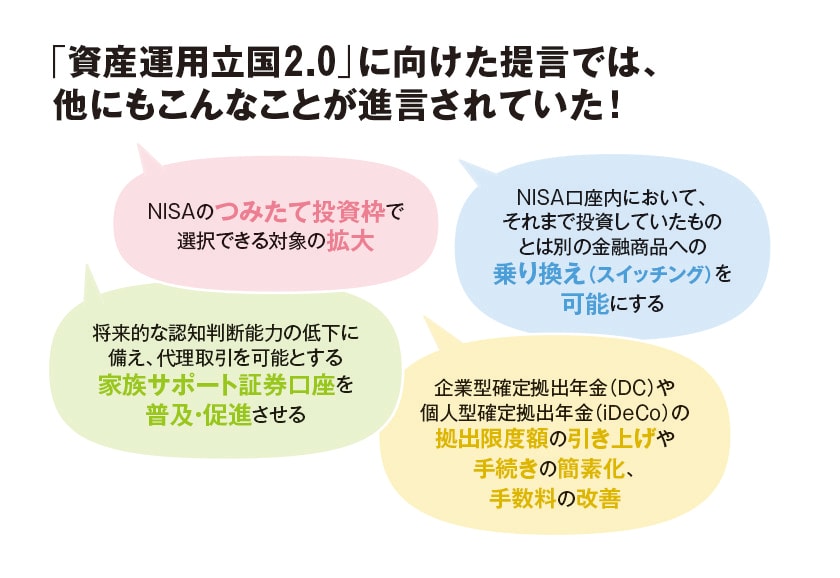
一般的に投資信託の多くは、運用で得られた収益を再投資に回し、利益が新たな利益をもたらすという“複利効果”を追求している。これに対し、毎月分配型は運用で得られた収益の一部をその投資信託の購入者に毎月還元する仕組みになっている。
分配金として受け取ってしまうと“複利効果”は得られないため、その分だけ運用効率が悪くなるのも事実だ。しかしながら、少しずつ利益が確定していくことに安堵感を抱く人や、年金のように定期的に分配金が入ってくることに魅力を感じるシニア層などの間で根強く支持されてきた。
ベストセラー『迷わない新NISA投資術』の著者であるファイナンシャルプランナーの菱田雅生さんは首を傾げながら指摘する。
「正直なところ、どうしてこのような構想が浮上したのかが不思議です。これまで金融庁は一貫して毎月分配型には否定的な見解を示し、NISAの選択肢から除外してきました。そもそも現行のNISAは65歳以上の方々も利用できる制度になっていますし、そういった世代の間で少しずつ取り崩していきたいというニーズが高いなら、その仕組みを整備すればすむ話でしょう。公的年金の受給は隔月なので、その空白月にNISAの運用資産を一部換金できるようにすればいいのです」
現行制度でも少しずつ取り崩すことは可能
実は、わざわざ「プラチナNISA」を創設しなくても、楽天証券の「定期売却サービス」や、SBI証券の「投資信託定期売却サービス」を利用すれば、すでにNISAの運用資産を部分的かつ定期的な解約は可能。楽天証券では定額・定率での取り崩しに対応しており、現時点でSBI証券の類似サービスの選択肢は定額コースのみでNISAには非対応。だが、今年中には定率方式も導入してNISAに対応する方針という。
「毎月分配型も選択肢に加える新制度を創設するよりも、証券業界に対して定期売却サービスの普及を促すことのほうが建設的でしょう。決算を毎月実施することでその事務コストもかかることから、基本的に毎月分配型は運用管理費用(信託報酬)などの手数料が相対的に高めの設定です。もしも『プラチナNISA』の創設を機に、65歳以上の世代専用の非課税枠が新たに設けられるとしたら、利用価値は高まると思われますが……」(菱田さん)
ただし、65歳以上に新たな非課税枠が得られたとしても、毎月分配型を選ぶのは言語道断だろう。続報では、毎月分配型のさらなる注意点について言及したい。
(金融ジャーナリスト 大西洋平)
こちらの記事もおすすめ 【続きはこちら】「プラチナNISA」で注目の毎月分配型投信 分配金に紛れる「タコ配」に要注意







































