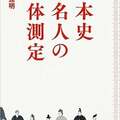天狗に憧れ、空を飛ぼうとした権力者がいた。細川政元は呪術や修験道に傾倒し、魔法を身に付けるための修行を理由に、あろうことか戦の最中に陣を抜け出そうとしたこともあった。そんな奇行の数々で知られる政元だが、実は室町時代と戦国時代を繋ぐ重要人物だった。
長年細川氏の研究をしている武庫川女子大学の古野貢教授は、著書「オカルト武将・細川政元」の中で、オカルトと政治が交錯する異色の武将の生涯を解説。同書から一部を抜粋して解説する。
* * *
空を飛ぶ「天狗」への憧れ
政元のオカルトへの傾倒を考える時に、彼には天狗への憧れがあったのではないか、と言われることがあります。では、当時の人々にとって天狗とはどのような存在だったのでしょうか?
山の先達である天狗は、英雄を教育する存在でもありました。源平合戦において平家を倒した源義経は、天狗から兵法を学んだとされています。そこから、修験道の修行によって義経のような力を身につけられるとなり、天狗への憧れも自然と生まれたのでしょう。
政元が天狗の存在をどこまで信じたかはわかりません。しかし、「今自分が置かれているどうしようもない状況を打破するためには、もっと新しい異質な力が必要だ」と考えるのはある意味ロジカルな帰結です。そこから「古典的にはお寺に頼る方法があるが、今ひとつ役に立たない」「修験道や天狗は怪しげでわかりにくくはあるけれど、なんとなく効果がありそうだからひとつやってみよう」という思考があったのではないでしょうか。
あるいはもっと即物的に、天狗の能力として語られるものを欲したところもあったのかもしれません。天狗は空を飛ぶだけでなく、速く動けたり、姿を消したりできたといいます。もちろん武力的にも役立ったでしょうが、政元は政治方面で活用したかったのではないか、とも考えられます。
例えば姿を消すことができれば、何らかの主張や政策を同僚や家臣に向けて提示した際、彼らが実際にどんなふうに受け止め、影で何を言っているかを、密かに盗み聞きすることもできるでしょう。ここで本音がわかっていれば、次に話すときの材料になるわけです。