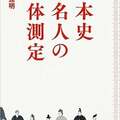オカルトを策に利用した政元
単純に言えば呪術や超能力が好きだった変人ということで話を終わらせることもできます。それはそれでひとつの捉え方であり、従来の細川政元を評価する基軸は実際にそうであったでしょう。
しかし、ただオカルトが好きだったからという説明では片付けられない点があります。たとえば延徳三年(一四九一)の頃なのですが、一人目の養子(後の細川澄之)を取るという話になった後、政元は「空を飛んで関東へ行く」と言い出します。北陸経由で越後国まで行き、そこから伊豆国のほうに下っていって、それから東海道を通って帰ってくるつもりだったらしいのですが、結局越後国で「ここから先へは行ってはいけない」と言われて帰って来る、ということがありました。
このようなエピソードに触れると「政元は勝手な思いつきで飛んでいった」ようなことをよく言われるのですが、政元は何も考えずに空を飛んで関東へ行こうとしたわけではなく、その振る舞いの背景には政治的な意図があったように見えるのです。
越後国から回ろうとしたのも、鎌倉府のナンバー2である関東管領・上杉氏がこの地にいたため、彼らとの関係性を構築しようとする意図があったはずです。実際、政元が関東へ行くのを諦めたのは、政知が病気で亡くなってしまったためとされます。
同じように修験道への傾倒についても、当時の修験道のあり方や、それに関わることのメリットやプラスがあるかどうかについて考えた方が、より正確に政元という人物について理解することができるでしょう。
たとえば、修験道の修行者たちは境界を越えることができる人々だった、という説明があります。日本では古代以来、全国を六十六の国に分け、国ごとに国司や守護を置き、国家として支配を行ってきました。
この各国の境界は支配の単位となるものなので、室町時代においてもそう簡単に越えられるものではありませんでした。この境目は一度戦国時代に壊れて曖昧になり、また江戸時代になると国ごとに藩が置かれて、復活あるいは再編成されていきます。その意味で戦国時代は地方支配の観点からすれば、非常に特異な時代だったと言えます。
しかし室町時代のような国の境目がはっきりしていた時代に、宗教的だったり産業的だったりする理由によって特別に境目を越えられる人もいました。修験道の修行者たちもそのひとつで、彼らは修行と称して尾根筋を走り回ります。
尾根筋は国境線となることが多く、本来は簡単に移動していい場所ではありません。しかし「修行だから」という理由で許されるわけです。鍛冶師や猟師のような人々も同じように自由に国境線を越えられたといいます。
つまり、政元が細川氏の頂点に立ちながらなかなか自分の思う通りに動くことができず、鬱屈した思いを抱える中で、自分のやりたいことを叶えるための武器として、修験者たちや鍛冶師や猟師などと繋がろうとした、ということはあり得ると考えられるのです。
それは当時の常識からすればなかなか変わっていることではあるのですが、政元がただの変人ではなく、自分なりの方法を模索して行動したと見れば、彼なりの筋は通っている、ということなのでしょう。
『オカルト武将・細川政元』では、呪術や空中飛行の修行に没頭した政元の人生や、将軍追放のクーデターにおける日野富子との交渉など、応仁の乱以降の“激動の時代”を解説しています。