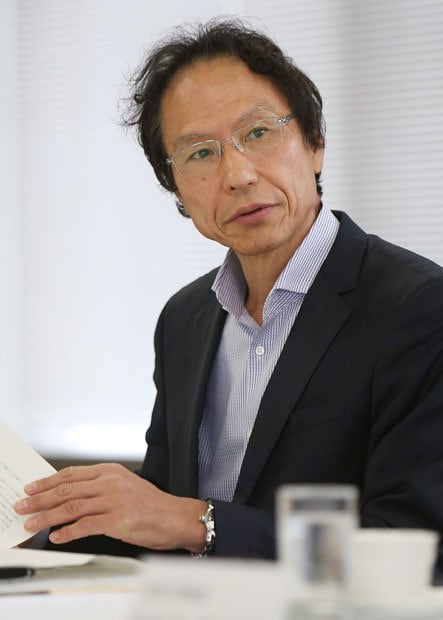
政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。
* * *
日本でラジオから第一声が流れた1925年3月22日、あの日から100年を迎えました。それを記念するNHKの特別番組「メディアが私たちをつくってきた!?」に出演する機会がありました。公共放送としての存在理由が問われ、テレビが「マスゴミ」「オールドメディア」と叫ばれる現在、NHKの中にも変わらなければならないという切迫感が募り、その方向をめぐり暗中模索の状況にあるのだと思います。
ならば放送100年の歴史を振り返れば、何か手掛かりが見つけ出せるかも……。それが先の特別番組になったのだと思います。番組に出て痛感したのは、テレビ(特にNHK)は時代の記憶装置であり、人々の生きた証しのアーカイヴで、歴史の記憶の貯水池だということです。
確かにラジオは戦争の中で産声を上げ、そのプロパガンダになるという不幸な歴史がありました。また、戦後のテレビは、明るい豊かさを映し出すナショナルメディアの主役に躍り出ましたが、成長という「国策」を寿ぐメディアになってしまったことは否めません。そんな中、番組では水俣病を「公害」として告発し、公共放送とは何かを問い直す検証を試みています。
国民的イベントであった紅白歌合戦ですら視聴率の低迷に喘ぐいま、ナショナルメディアとは言えず、60年代後半の公害告発の国民的な影響力をテレビに期待することは不可能なのかもしれません。それでも非営利的な公共空間のプラットフォームを作り、その場にインターネットなどの新しいメディアを巻き込み、その公共放送としての役割を果たすNHKへと脱皮していくことは可能なはずです。
現状維持(ステータス・クオ)は、NHKにとって事実上、なだらかな死を意味しています。変わらなければなりませんが、それが「楽しくなければテレビではない」という方向になることはもはやありえません。また、イーロン・マスク的な省力化と民営化に走ることは、公共性のメディアの死滅を意味しています。テレビは非営利的な公共空間をいかにして作り出し、それを通じて民間や私的な活動をより活性化させることが出来るのか。NHKが正念場にあることは間違いありません。
※AERA 2025年4月7日号








































