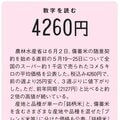社員の労働時間を減らせば、生産性が同じ場合、当然だが会社の売上は下がる。なので残業を減らして売上を維持するためには、社員の生産性を上げる必要がある。だが、過労死問題となると、そこで言われることは「10時間かかっていた作業を8時間でこなせるようにすれば残業はなくなる」といった議論ばかりだが、これは実に些末なことだ。僕に言わせれば、企業における生産性とは「売れる商品を生み出すこと」である。いくら優秀な営業マンでも、売れるはずのない商品を売らされていたら生産性が上がるはずもない。企業においては、売れる商品を生み出せる人間が有能。そうでない人間は無能なのだ。
そして、売れる商品を作るというクリエイティブな仕事は、労働時間とはほとんど関係ない。長時間労働をしたからといってクリエイティブな仕事ができるわけでもない。むしろ、仕事時間が少ないほうが、良い仕事ができたりもする。
獨協医科大学越谷病院 こころの診療科の井原裕教授が書いた記事によれば、「人間というのは高度に知的な作業は、1日のうち、ほんの数時間しかできない」という。さらに、「睡眠不足というのは、一時的に頭が悪くなる状態のこと」だともいう。つまり、ちゃんと睡眠時間をとり、1日のうち、数時間集中して知的作業を行うことが、クリエイティブな生産性を上げることにつながる、ということだ。平日の昼間からプールで泳いでいるオヤジ社員が生産性の高い仕事ができるのも、そうした理屈からだろう。
つまり、過労死を防ぎながら社員の生産性を上げるためには、残業をなくせばよいというものではない。社員が、自分の知的リソースを、どのタイミングでどれだけ使うかを自由に決めることができる――そうした自由な働き方を許容することが有効なのである。もちろん、「知的リソースの活用」とは、仕事のアウトプットだけではない。たとえば、勤務時間中に映画を観に行くといったインプットも含めてのことだ。
実際、かつての電通マンほどではないにせよ、いまでも多くの企業で高い生産性をたたき出している社員はけっこう自由だ。さすがに朝は定時に出社するが、昼間に会社の仕事とはまったく関係ない人間と喫茶店でお茶をしていたりする。会社にいたとしても、会議室で雑談ばかりしていることもある。もちろん、夜は無駄に残業して、残業代を稼いだりはしない。定時になればさっさと退社して、社外の人間と飲みに行ったりしている。そして、そこで生まれたネットワークを活かして新しい仕事を作ったり、自分の価値を高める情報やインサイトをゲットしたりしている。そうした働き方をしている人たちが過労死とは無縁であることは言うまでもない。