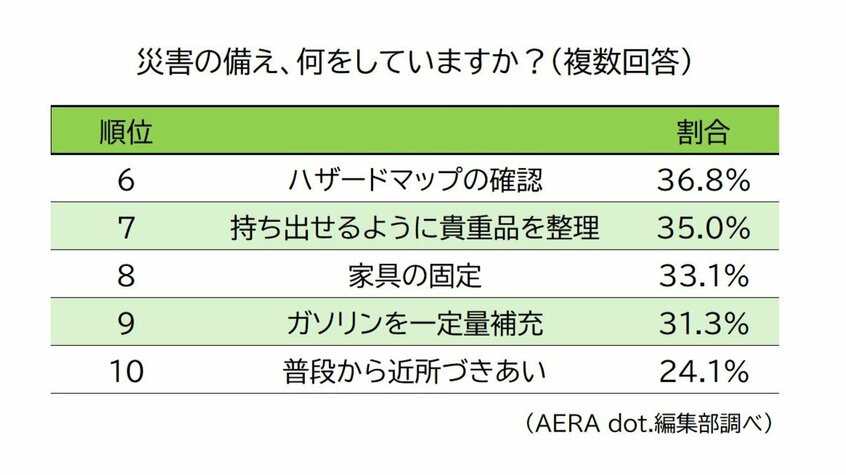
備えは個人でできること以外にも
災害が起きたら、どんな状況になるか。不安に思っていること、心配なこととして、「ライフライン(水や電気、トイレなど)の寸断」「家屋の倒壊」「避難所での不自由な生活」「家族の安否確認」など、さまざまな声が挙がりました。
個人でできる備えのほかに、防災訓練などへの参加、隣近所の人たちとの連携、という形もあります。
今回のアンケートでは、このようなコメントも寄せられました。
「学校の引き取り訓練の際に、毎年1度は子供と公衆電話の位置を確認し、子供に常備させているテレホンカードと小銭を使って祖父母に電話をかけています。その際には地震があった際に危険になるであろう壁や看板、工事現場などを確認しています。
通学路はスクールゾーンというわけではなく少し遠回りになっても災害時に安全なルートになるよう途中に避難所の前や幼稚園や学校の前を通るよう設定しました。子どもにはもしもの時のために非常時の笛を持たせています」(50代、女性)
「落ち着いて対応する為に、日頃から、防災館等地域にある、実際の行動の訓練後できる施設での体験は役立ちました」(60代、女性)
「マンションで自主防災会組織を作っており、学区の防災会組織にも参加している」(70代以上、男性)
今回のアンケートでは、災害に対する備えを「していない」という回答が3割ほどありました。その理由として、「備えが必要と思うが、何をしたらいいのかわからない」が40.4%、「備えが必要と思うが、時間や費用、手間がかかるからやっていない」が39.4%でした。
災害はいつ、どんな形で起こるかわかりません。
今回のアンケートの回答も参考に、ご自身にとって簡単に、気軽にできることから始めてみてはどうでしょうか。
(AERA dot.編集部)





































