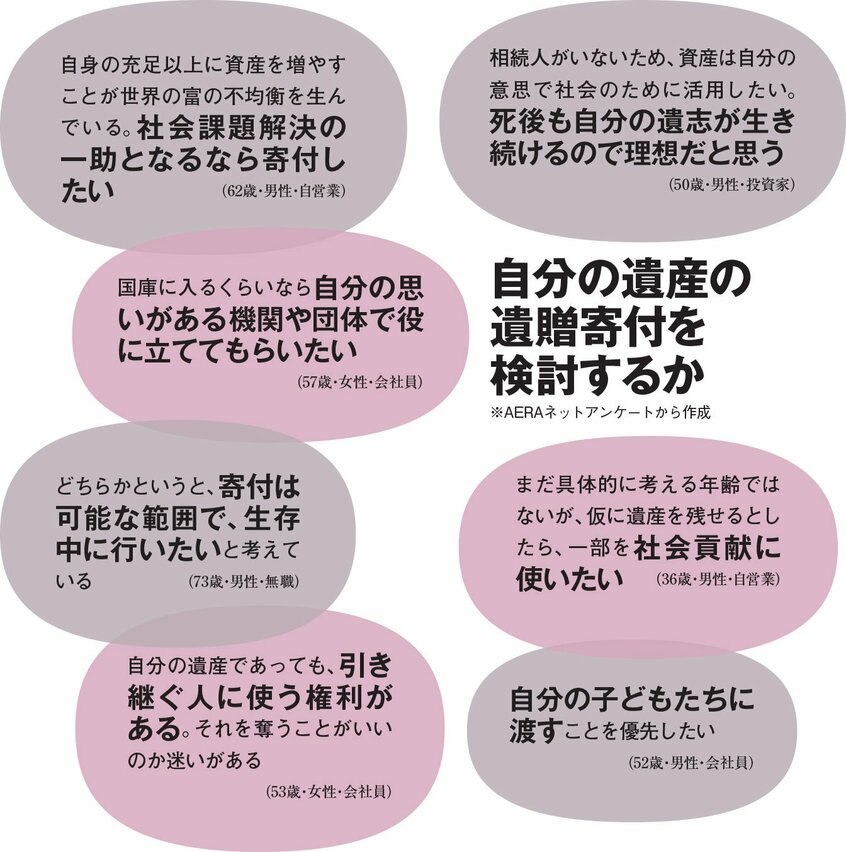
故人の思いに触れる
父の思いを酌み、適切に遺産を活用してくれる団体かどうかは時間をかけて判断したという。少額を寄付してきたほか、2年ほどボランティアとして民際センターの活動に参加、その後、「父の遺産を寄付したい」と切り出した。センターからラオス南部の学校がない集落を提案され、15年11月に開校した。井上さんはこう振り返る。
「開校式に参加した時は、父の魂がそこにあるような気がして、すごく幸せでした。『お父さん、よかったね』と伝えました。2年後にも現地を訪れ、実際に学校に通う子たちの生活を見ることができました。大変な生活の中でも頑張って勉強する子を見ると、もしかしたらそれが将来、地域を豊かにして、国を変えていくかもしれないと感じたことを覚えています。今も、その学校の子どもたちに奨学金を送っています。私の財産も、子どもたちに継がせるだけでなく、一部は遺贈寄付をしたいと考えています」
遺贈寄付は、「生きた証しを残す寄付」「未来へ思いをつなぐ寄付」などと言われている。そして、遺族にとっても、折々に故人の思いに触れる機会になっているようだ。(編集部・川口穣)
※AERA 2024年8月5日号より抜粋







































