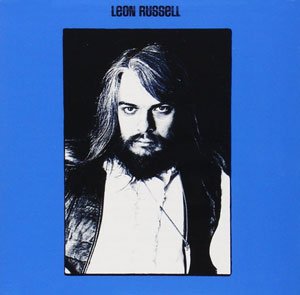
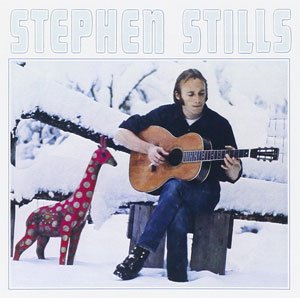

ディレイニー&ボニーとの出会い、それにつづくブラインド・フェイス分裂のあと、エリッククラプトンは、より自由なスタンスでセッション・ワークに取り組むようになっている。ただし、やはりこの時期の仕事に関してもセッション・ワークという言葉はなんとなく馴染まない。「親しい音楽仲間の創作活動への協力」と呼んだほうがいいだろう。
ディレイニー&ボニー&フレンズとジョージ・ハリスンについてはすでに紹介したが、当然のことながら、この人脈のなかでの仕事が目立つ。たとえば69年の秋には、そのサークルの音楽監督的存在だったリオン・ラッセルのファースト・アルバムに貢献している。正確なクレジットはなく、レコーディング自体がフリー・セッション的なものだったそうだが、《プリンス・オブ・ピース》などで明らかに彼のものとわかるギターを聞かせている。同時期・同人脈の仕事としては、ジョージ・ハリスンがプロデュースを手がけ、アップル・レーベルからリリースされたビリー・プレストンの2枚のアルバム、ネイティヴ・アメリカンのギタリスト、ジェシ・エド・デイヴィスのファースト・アルバムも忘れられない。
1970年春には、アーメット・アーティガンの勧めがあってのことだと思うのだが、すでにCSNYで巨大な成功を収めていたスティーヴン・スティルスのファースト・ソロ・アルバムに参加。《ゴー・バック・ホーム》でシャープなソロを弾きまくっている。なおこのアルバムには、ほとんど正式な形でのセッション・ワークを残さなかったジミ・ヘンドリックスも協力していた。別の曲とはいえ、クラプトンとヘンドリックスが顔を揃えた、おそらく唯一の作品となっている。
じつは、スティルスとクラプトンは67年に出会っていた(バッファロー・スプリングフィールドとクリームの時代)。ローレル・キャニオンでニール・ヤングも含めた仲間たちとマリファナを吸っていると、警察に踏み込まれたのだが、スティルスは直前に逃げてしまったというエピソードも残されている。その奇妙な友情がここで実を結んだというわけだ。
このあと、ご存知のとおり、空白の3年間があり、74年に復活したクラプトンは、セッション・ワークにもあらためて取り組むようになっている。この時期に目立つのは「憧れの存在」でもあったザ・バンドとの交流で、76年春には彼らとボブ・ディランらの協力を得て『ノー・リーズン・トゥ・クライ』を録音したあと、そのままの流れでベース奏者リック・ダンコのソロ・アルバムに参加し、秋にはあの『ザ・ラスト・ワルツ』にも出演した。
アルバム『リック・ダンコ』でクラプトンがギターを弾いたのは、《ニュー・メキシコ》。派手さはないが、ガース・ハドソンのアコーディオンと絡みながら、じつに味わい深いプレイを聞かせている。 [次回10/21(水)更新予定]



































