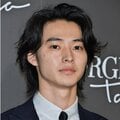「インクルーシブ」「インクルージョン」という言葉を知っていますか? 障害や多様性を排除するのではなく、「共生していく」という意味です。自身も障害のある子どもを持ち、滞在先のハワイでインクルーシブ教育に出合った江利川ちひろさんが、インクルーシブ教育の大切さや日本での課題を伝えます。
* * *
今年も残りわずかとなりました。12月は私と息子の誕生月でもあり、特別な1カ月なのですが、それ以上に12月と言えば、子どもたちを連れてハワイでの生活を始めたという大きな思い出があります。もう12年も前のことですが、今の生活の原点になるできごとでした。今回は当時から現在までのことをまとめて書いてみようと思います。
息子にお友達ができることを願って
その前年(2010年)の12月に息子は3歳になりました。同じ学年のお子さんは4カ月後の4月から幼稚園の年少さんになる年です。
以前、息子の受け入れ可否を問い合わせた園すべてから「歩けないと入園は難しい」と言われていたため、【3歳のお誕生日までに歩くこと】が、息子が2歳からの1年間の最大の目標でした。でも、結果は、歩くどころかひとりで立つこともできない状態でした。
私が住む地域にある幼稚園はすべて私立のため、合理的配慮の提供は義務ではなく、各幼稚園ごとに入園の選抜をすることができます。「人手不足」「段差がある」「経験がない」など理由はさまざまでしたが、どの園も独歩ができなければ受け入れは不可、とのことでした。
もしかすると、上に重症心身障害児の長女がいなければ、「障害があるから仕方ない」と諦めたかもしれませんが、長女が通っていた児童発達支援センターは長女のように言葉でのコミュニケーションが取りにくいお子さんが多く、息子が通ったら話す相手はお友達ではなく先生になることが分かっていました。息子を幼稚園に入園させたかった理由は、息子にお友達ができることを願ったからです。軽度障害者としていずれ自立しなければならないのなら、少しでも早い時期から集団生活に入り、社会性を身に付け、しっかりとした教育を受けてほしいと考えるようになったのです。
市の担当者の言葉に傷つき
そんな時、長女が通っていた児童発達支援センターで就学相談会がありました。私は長女ではなく息子の相談をするために予約を入れ、市の担当者と話をしました。
「身体障害者手帳が2級でここ(頭)が大丈夫な子、見たことがないんだよね。お母さんは毎日一緒にいるから息子さんとコミュニケーションが取れるだろうけど、本当に知的な発達に遅れはないの? お母さんが大丈夫だと思っているだけじゃないの?
僕は最後の現場が支援学級だったからよく分かるんだけど、身体が不自由な子は頑張って普通級で学ばせるより、養護学校の方がその子のためだよ」
3歳~4歳頃の息子は、座っていればどこにでもいる男の子だったと思います。言葉を話し、ひとりで食事をし、トイレのタイミングも伝えることができました。でも当時はまだ、息子のように膝下のみの障害は珍しく、就学相談の場であってもなかなか状況を理解してもらうことは困難でした。
特にこの時は担当者の言葉に私自身がひどく傷つき、もしもこの先、何とか幼稚園に入園することができても、就学相談をしている自治体の部署がこの考えでは、また就学時に同じことが繰り返される気がしました。