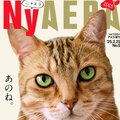インターバル速歩とは、「早歩き」を3分間したら、「ゆっくり歩き」を3分間。これを交互に繰り返す。ここで言う“早歩き”の指標は最大酸素消費量70%で、「3分歩けば息がはずむ速度」「息が上がるくらいのキツさ」が目安。1週間にインターバル速歩計120分(早歩きが60分)が目標だ。インターバル速歩を1日30分やれば週4日、週末だけなら土日に60分ずつで達成できる。
「過去15年間、遺伝子データ2200人を含む1万人のデータベースを解析しました。インターバル速歩を5カ月間行うことで筋力など体力が平均15%増加し、糖尿病などの生活習慣病指標が20%改善、うつ指標が40%改善、医療費が20%削減されることがわかりました」(能勢特任教授)
カギは、ミトコンドリアだという。ミトコンドリアはすべての細胞内に存在し、ブドウ糖や脂肪酸を燃やして生きるエネルギーを得る。加齢で筋力が落ちると、筋肉内のミトコンドリアが劣化する。筋力が低下すると人の活動も減り、筋肉以外の臓器の代謝も低下し、全身のミトコンドリアが劣化する。
「劣化したミトコンドリアは活性酸素を排出し、細胞や組織を傷つけ、炎症反応が起こる。脂肪細胞に起これば糖尿病、免疫細胞に起これば動脈硬化や高血圧、脳細胞に起こればうつ病や認知症、がん抑制遺伝子に影響が及べばがんを招く。回避するには、筋力を向上し、ミトコンドリアの活性化をはかる必要があるのです」
活動的に動けるようになるには、筋収縮力を支える「速筋」、筋持久力を支える「遅筋」の両方を保つ必要がある。速筋には筋トレ、遅筋には有酸素運動が有効で、両方の運動を同時にできるのがインターバル速歩だ。
「『大股』『直立』『手を大きく振る』。この三つだけ、意識してください。高強度で安定して歩けるフォームです」
(ライター・羽根田真智)
※AERA 2023年11月13日号より抜粋