
「ChatGPT(チャットGPT)」の登場で、これまで以上に英訳も和訳も作りやすくなった。これからの外国語教育で求められることは何か。東京外国語大学理事の青山亨さんに聞いた。AERA 2023年7月10日号の記事を紹介する。
* * *
チャットGPTの登場で、「大学における外国語教育」はどう変わるのか。東京外国語大学理事の青山亨さんは、「生成AIが一般化する社会だからこそ、外国語大学の学生はしっかりと外国語を学ぶ必要がある」と話す。なぜか。
言葉によるコミュニケーションには、大きく二つのあり方がある。一つは、事実を事実として伝える、知識ベースのコミュニケーション。ホテルの予約をしたいとき、「何月何日に予約をお願いします」といったもの。もう一つは人間関係の形成のためのコミュニケーションだ。
「お互いに信頼できる関係の構築。そのためのコミュニケーションは、機械に頼り、ただ事実のやりとりを正確にやるだけでは不十分です。事実の翻訳だけではわからないニュアンスや、相手の文化、歴史も理解した上でのコミュニケーションが必要。大学で求められている外国語教育は、そのレベルの教育だと考えています」
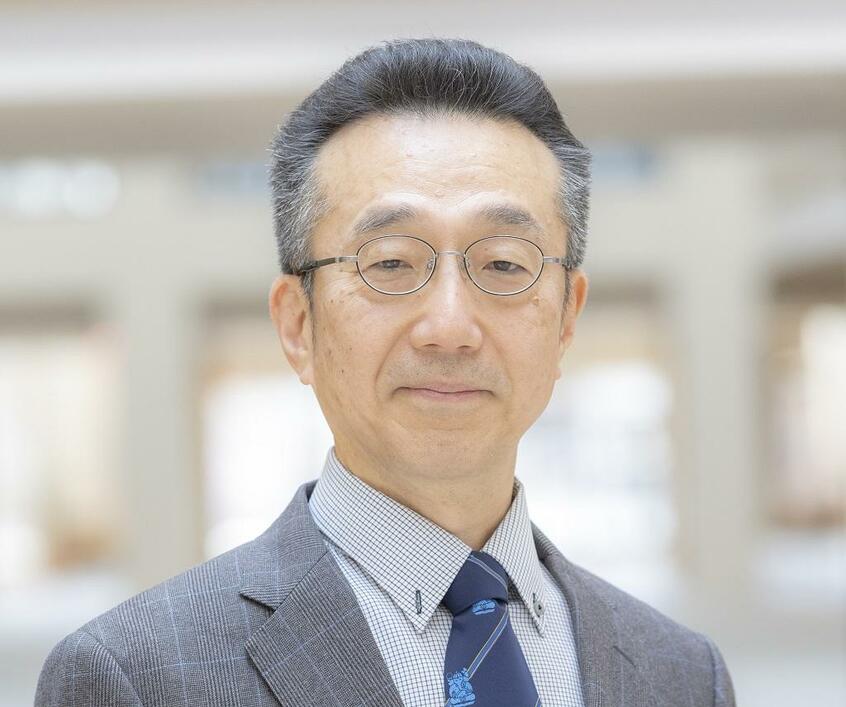
会話ができるチャットGPTの技術は普遍的な広がりのある大変革であり、「期待するところも大きい」と青山さん。ただ、それを使いこなす知識、技能が使う側に身についていることが条件だと釘をさす。
「従来の機械翻訳でも言えることですが、チャットGPTで返ってきた翻訳が文法的には正しくても、『その状況で適切な表現になっているか』は別の話。同じ言葉でも、ビジネス文書の翻訳なのか、ラブレターの翻訳なのかで使い方は変わってくる。そこを判断できる力を身につけてほしい。そこまで達していないのに初めからチャットGPTにお任せでは、本人にその力がいつまでもつかない。最も懸念するところです」
東京外大では、頭ごなしにチャットGPTを「使うな」というメッセージは出していない。5月19日に教員に示された指針では、提出されたリポートをもとに口頭試問を行い、内容を学生がよく理解しているか確認する方法や、リポートのアイデアをAIから得た場合にはどのように使ったかを「はじめに」で明示させる方法などが示されているという。
「生成AIは有効なツールになり得ると思います。しかし、あくまでもツールであり、『最終的な成果物は自分のものである』と自信をもって言えるものにしてほしい。学びとは気づきの積み重ねであり、時間をかけないとできない面もあります。チャットGPTをツールとして使うその先にある、人間関係を形成するためのコミュニケーションを外国語でできる能力を、学生一人ひとりが時間をかけて積み上げていく必要があります」
(編集部・小長光哲郎)
※AERA 2023年7月10日号より抜粋






































