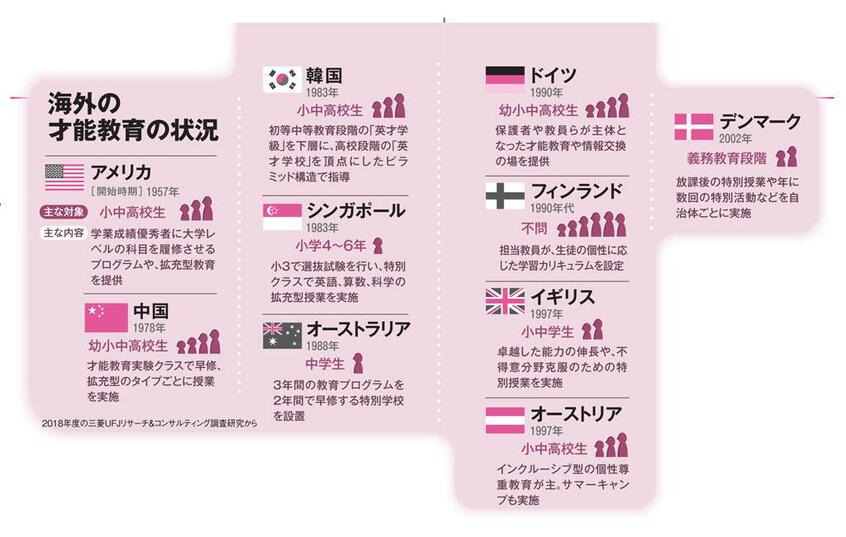
「ギフテッド」という特性をご存じだろうか。日本では長らく、その実態が知られてこなかったが、近年文部科学省も特異な才能がある子どもへの支援に乗り出した。『ギフテッドの光と影』(朝日新聞出版)の著者が、日本の現状と課題を伝える。AERA 2023年5月29日号の記事を紹介する。
* * *
ギフテッドの人たちの中には、心ない言葉をかけられた人も少なくない。取材で話を聞いた当事者の中にも、高IQであることをカミングアウトしたところ、「IQが高いのを自慢している」と批判された人もいた。
また、ギフテッドと聞くと、「ずば抜けて勉強ができる超天才」をイメージすることもあるかもしれない。だが、幼い頃にアインシュタインの相対性理論を理解する、というようなギフテッドは、ごくごくわずかな存在だ。多くのギフテッドは、IQが120~130の知能指数を持ち、クラスにも複数人いるかもしれない、意外と身近な存在なのだ。
「頭がいいからいいじゃない」
「勉強ができるだけで、人間としてはでき損ない」
そんな言葉をかけられた当事者もおり、まだまだギフテッドに対しての正しい認知は進んでいないのが現状だ。
そんな中、2021年には文部科学省が有識者会議を立ち上げた。議論になったのは、どのような子どもたちを支援の対象とするかの定義づけだった。
22年秋にまとめられた提言では、IQなどをもとにして才能を定義すると、高IQの人を選抜する動きが出てくるとして、「定義はしない」と結論づけた。定義した場合の弊害として挙げられたのは次のような点だ。
●選抜のための過度な競争が発生する
●入学者選抜へ活用される
●経済状況によるプログラムへの参加機会の格差が生ずる
●学校現場の分断や同級生からの差別
●児童生徒が過度な期待を背負う
その上で、提言では「特異な才能のある児童生徒の困難に着目」した。困難とは、例えば学習や学校生活でのトラブル、不登校になっている場合などが想定されている。学校などで困難を抱える子どもを把握し、まずはそれを解消する支援をしてみよう、ということだ。困難の原因が、特異な才能があるためだったことがわかれば、その困難を解消することで、元からある才能を伸ばすことにもつながるのではないか、と有識者会議はまとめている。



































