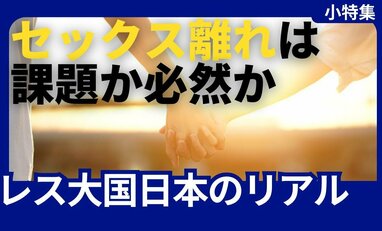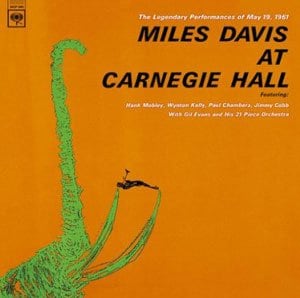
マイルス・デイヴィスのアルバムは、決して誇張や宣伝文句ではなく、すべてが必聴傾聴に値するが、いつのまにか順位のようなものがつけられ、常に上位に選ばれるアルバム以外に注意が払われることは意外に少ない。というのも上位作の数がまた多く、聴いても聴いても聴き飽きるどころか次から次へと発見の連続で、なかなか次のアルバムにうつることができないからだ。
『アット・カーネギー・ホール』は、同じくライヴ盤の『フォア&モア』や『マイルス・イン・ベルリン』のように上位にランクされることは少ないものの、絶対に外すことのできない、それこそ必聴のライヴ盤であるということを、まずは声を大にして言っておきたい。こういうものすごいライヴ盤が上位ランキングの常連でないところがマイルスの恐ろしさであり、なるほど「マイルスに凡作なし」とはこういうことなのだなと激しく納得してしまう。
1961年5月19日(マイルス35回目の誕生日の1週間前)、ニューヨークのカーネギー・ホールでライヴ・レコーディングされた。マイルスとしてはライヴ・レコーディングする気はなかったが(新曲を演奏する予定はないという、いかにも明日しか見ていなかったマイルス的理由による)、プロデューサーのテオ・マセロが「それはもったいない」と会場備え付きの機材を使ってこっそりテープを回し、後日テープを聴いたマイルスが、「へえ、こんなに良かったのか」とアルバム化が実現した。録音状態が他のマイルスのライヴ盤と異なるのは、どうやらそういうことが原因らしい。
テオ・マセロに感謝しよう。もしテープを回していなかったら、この圧倒的にして歴史的な演奏は永遠に失われていただろう。たしかにマイルスが言うように新曲はないし、中心となるクインテットのメンバーは、同時期のライヴ盤『ブラックホークのマイルス・デイヴィス』と同じではある。しかしギル・エヴァンス編曲指揮のオーケストラとの共演がライヴで聴けるのはこのアルバムのみ、しかもクインテットの燃え上がり方が、ジャズ・クラブ(『ブラックホーク』)とカーネギー・ホールではまったくちがう。どちらもすばらしいが、ピーンと張りつめたような緊張感という点では、カーネギー・ライヴのほうが数倍勝っているように思う。まあ『ブラックホーク』はクラブならではの「寛ぎを含んだ緊張感」が魅力ではあるのだけれど(言ったでしょ、マイルスはすべてが必聴傾聴に値すると)。
さあ《ソー・ホワット》が始まった。ギル・エヴァンスの繊細な指さばきによって魔法をかけられたオーケストラが、荘厳にして「何かが始まる予感」を抱かせてやまないオープニングを奏で、おお、あのテーマがやってきたではないか。ぼくはこの瞬間、いつもゾクッとする。そしてクインテットだけのパートに移行してからのスウィング感のすごいこと! いつもは控え目なハンク・モブレーがここまで過激にサックスを吹くことはあまりないのではないか。モブレーをはじめ、とにかくこの日のクインテットには何かが憑依しているような凄みすら感じる。スウィングの神かもしれない。急いでつけ加えておこう。この日の演奏は、モブレー時代のクインテットにとって最後のセッション。燃え上がって当然というものだろう。しかも舞台はカーネギー・ホールなのだから。《ノー・ブルース》と《オレオ》の熱すぎる演奏は、最後の燃焼という表現がふさわしい。
それにしてもマイルスの堂々たる演奏ぶりはどうだ。トランペットから放たれる一音一音が、その音の在るべき場所に向かって弧を描いて着地していくさまは、一流アスリートの演技の如く、ため息が出るほど美しい。これを一発勝負のライヴで軽々とやってのけてしまうのだから、ますます恐れ入る。他の演奏が収録された『モア・ミュージック・フロム・カーネギー・ホール』と合わせて、さあこれでぼくたちも歴史の目撃者だ。[次回8/25(月)更新予定]