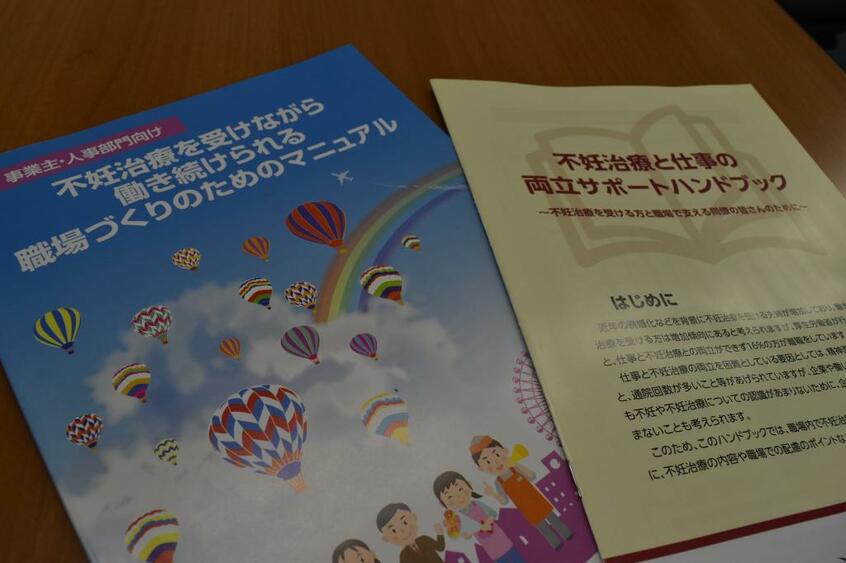
誰の精子かわからないまま使われ、生まれてきた子供たちの多くが「自分のアイデンティティの半分が空白」と訴える。彼ら・彼女らの「出自を知る権利」はどう保障されるべきなのか。AID[非配偶者間人工授精]が浮かび上がらせる問題の本質について、10年以上にわたり取材を続けるジャーナリスト大野和基氏の新刊『私の半分はどこから来たのか――AIDで生まれた子の苦悩』(朝日新聞出版)から一部抜粋・再編して紹介する。
※前編「夫のものではない精子で妊娠・出産する『AI』」 生まれた子供が経験する“喪失体験”の実態」よりつづく
* * *
■自分は何者なのだろう
横浜市立大学で内科医として勤務する加藤英明は、29歳のとき自分がAIDで生まれたことを偶然知った。そのとき、家庭内で違和感や緊張感を感じることはなかったので、よけいにだまされた気持ちになったという。AIDで生まれた人の中には、親に告白されたとき、今まで何かおかしいと思っていたことについてすべて納得がいった、という経験をした人もいる。
加藤は父親に問い質そうと思ったこともあったが、父親にこの話を持ち出す気にはなれなかった。母親は、自分をAIDで産んだと認めたことを父に言っていないかもしれない。しかし、自分が真実を知っていることを、父親が母親から聞いて知っているのであれば、そのことについてお互いに何も言わないのは、それはそれでばつが悪いとも思った。子供は、祖父母の存在を意識しながら育つことがある。生きていようといまいと、祖父母がどういう人物であったか、具体的なストーリーがそこにあるので、血縁を遡さかのぼることでアイデンティティが確立される。だが、AIDの場合、匿名の精子が提供されるので、父方の血縁関係がすっぽり抜けて空白状態になる。
「自分のアイデンティティの半分がふわふわ宙に浮いている気持ちになった。自分は何者なのだろう。どこの誰なのだろうと思った」。加藤はそう振り返る。私がアメリカやイギリスで取材したAIDで生まれた人も異口同音に「アイデンティティの半分が空白状態」である気持ちを吐露していた。





































