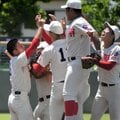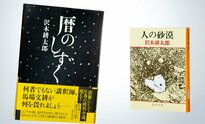「実習時間が増える分、今まで以上に医学部生の負担は増えます。しかし、患者さんと接する実践的なカリキュラムの増加は、やる気のある医学生にとって有益だと思います」(奥村館長)
各大学はカリキュラムの改革を急ピッチで進めている。通達のあった10年は、認定基準を満たす大学はゼロだったが、20年2月現在、38大学になった。
医療ガバナンス研究所理事長の上昌広医師は、医学生に海外に出ることを勧めている。
「技術さえあれば、どこでも仕事ができるのが医師の特権です。日本は人口減少が進み、将来的には医師が飽和状態になるでしょう。これから、アジアの時代が来る。若い医師はアジアの国々に飛び込んだ方がいい」
灘高校出身で東京大学医学部4年の小坂真琴さん(22)の思い描く進路は明快だ。
「地理的に見ても、九州はアジアに通じている。首都圏とは違う場所で働くことで、学べることも多いと思う」
卒業後は福岡で研修し、九州を足がかりにアジアを目指すつもりだ。高校、大学と最高峰に進んだ華麗な経歴に思えるが、「医師になれば、出身大学は関係ない。一からのスタートです」とおごりはない。
小坂さんは、大学2年生のとき知り合いの医師に同行し、ネパールを訪問。地震による粉塵がもたらす肺疾患の調査を見学した。その経験から、「臨床を行いながら、社会へ関心を持ち、問題解決に向けて行動する医師」になりたいという。(ライター・柿崎明子)
※AERA 2020年3月2日号より抜粋