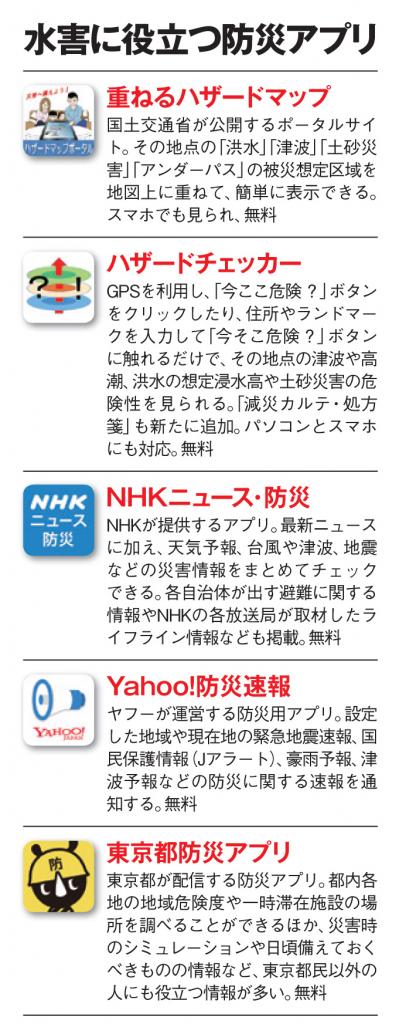
未曽有の豪雨が各地で起こる昨今、日頃から防災への意識を持つことが重要になってきた。地下鉄や地下街、アンダーパスなどで浸水に遭遇したらどうすべきか、専門家に聞いた。
* * *
「日本の防災における最大の課題は、リスクに向かい合っている時、当事者意識が欠けていること。自分ごととして捉えることができていないこと」
こう指摘するのは、東京大学特任教授の片田敏孝さん(災害社会工学)だ。
かつて日本人は、自分の命は自分で守る「自助」の意識を持っていた。しかし約5千人の死者が出た59年の伊勢湾台風を機に、61年に災害対策基本法が施行され、防災を国、都道府県、市町村の「責務」とした。その結果、住民の行政依存が高まり、危険を過小評価する「正常性バイアス」が働きやすく、リスクと向き合っても当事者意識をなかなか持てなくなったという。
今年7月、鹿児島市の全住民に避難指示が出た際も、実際に避難した人は0.6%だった。
そうした中、国の中央防災会議の作業部会は昨年末、西日本豪雨を受け、5段階からなる「警戒レベル」の導入と、「住民主体の取り組み強化」を打ち出した。これまでの防災の考え方から大転換を迫り、災害時における行政の限界を認め、行動の主体は一人一人だというメッセージを発した。以前から行政に甘える「災害過保護」の問題点を指摘し、同作業部会の委員も務めた片田さんは言う。
「大事なのは、避難する住民の主体性。たとえば河川の氾濫による水害の避難指示が出た時、マンションや高台に住んでいる人はそのまま家にとどまるのもいい。避難が、自分で判断した行動結果かどうかが大切です」
水害に遭遇した際、どう避難すればいいのか。
防災・危機管理アドバイザーの山村さんは、地下街にいて水が浸水してきた時は「垂直避難」が原則と言う。
「水は地下に一気に流れ込んでくる可能性があるため、早い段階で少しでも上の階に避難するのが肝心です。普段よく利用する地下街などはあらかじめ避難口を調べておき、出張先の場合は避難誘導灯などに従う。エレベーターは途中で止まる可能性があるので階段を使います」
地下鉄や列車に乗っている時に水害に遭ったら、車両から出るのは危険。基本的には乗務員の指示に従ってほしいという。
冠水したアンダーパスに車が誤って入った時は、
「水圧はドアの表面積によっても違うため、水圧で運転席のドアが開かなくても、後部座席のドアは開く可能性がある。ドアや窓も開かなくなったら、脱出用ハンマーで窓ガラスを割って脱出するしか方法はない。フロントガラスは割れにくい構造なので、運転席横の窓ガラスの中央付近を狙う。車外に出たら、進行方向は水深が深くなっている可能性があるため、進行方向とは逆の方向へ逃げてほしい」
とアドバイスする。






































