


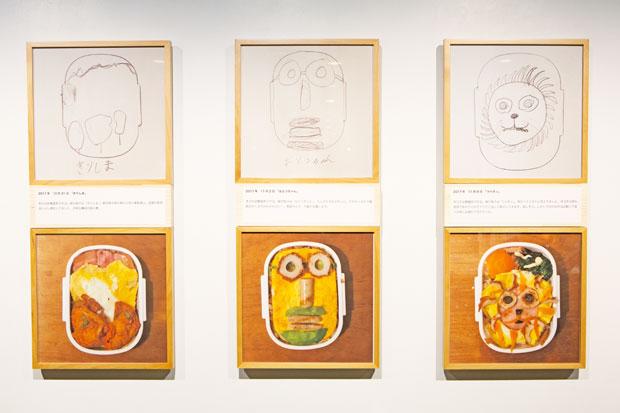
東京都美術館(ギャラリーA・B・C)で開催中の展覧会「BENTOおべんとう展─食べる・集う・つながるデザイン」。全国の「普通の人」のお弁当を訪ね歩き、その人のポートレートとともに写した「おべんとうの時間」を撮り続けてきた写真家の阿部了さん(55)をはじめ、7人のアーティストが「おべんとう」をテーマに作品を発表している。
* * *
阿部さんも今回、普段と少し視点を変え、お弁当を「食べている人」を写したシリーズ「ひるけ」を発表している。
「『おべんとうの時間』を撮りながら、撮りためていたものです。最初は食べてるところなんて人に見せたくないだろうな、と遠慮して、お弁当とポートレートだけを撮っていたんです。でも何人かにお会いするうちに、お弁当を食べてるときに、ものすごくいい瞬間や、いい表情が出てくることがわかってきた」(阿部さん)
「ひるけ」は「昼餉」の読み方のひとつだ。昼どき、お弁当に向かう人々の表情は、どこか無防備で「素」のように感じる。
「『写すの? かんべんして。食べた心地しないよ』って言われることも多いんです。だから『もう(撮影)終わりです』ってウソついて(笑)、遠目から観察して、半分くらい食べ終わったころにするすると近づいて、また撮影したりもする」
食べるという行為には、どこか自分自身と向き合うところがある、と阿部さんはいう。
「食べているときって基本的に何にも考えていないでしょう。だから『素』になる。僕はその瞬間が好きなんです。その表情から、お弁当を作ってくれた人や家族、その地域など、その人の背景にあるものが想像できるから」
会場を見てまわった阿部さんは「おべんとう展」に共通するものがあると感じたという。
「どの作家の方の作品を見ても、やさしいし、愛情があるよね。お弁当って人間のそういう部分に結びつくものなのかな、と思う」
会場には外国人の姿も多い。阿部さんの写真集『おべんとうの時間』も台湾、フランス、韓国、中国語に翻訳されている。
「海外では『なんでこんなにいろんなものをコチャコチャと入れるの?』という、日本人の細かさや美意識への反応もあるけれど、『お弁当を通じて、日本人の普段の姿や生活に興味を持った』という人が多い気がする。知っていそうで知らない、日本人の“素”の部分をおもしろがってくれるのかな」
誰かのことを思い、誰かのために作るお弁当は国境を超えて「やさしさ」を運ぶのかもしれない。改めて、阿部さんにとって「お弁当」とは?
「一言でいうと“そこから日本が見えてくるもの”かな。時代や世界の移り変わりも、お弁当に反映されると思うんです」
例えば、戦後に「ドカ弁」と呼ばれた弁当は、弁当箱に米を詰め、その上に梅干しをのせ、さらに蓋のほうにも米を詰めて“ご飯のサンドイッチ”のようにしたものだと、取材先で年配者に教わったことがある。それは物がない時代に労働者がおなかいっぱい米を食べるための工夫でもあった。
「100年後にもお弁当は必ずあるだろうし、そのときの時代も世界もそのなかに当然入ってると思うんです」
(ライター・中村千晶)
※AERA 2018年9月24日号より抜粋





































