


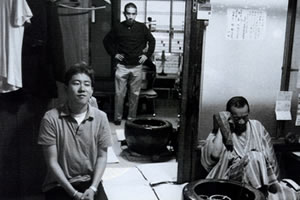
――なぜカメラですか
じつは落語家になったのもカメラを始めたのも、魂胆は一緒なんです。ぼくは鹿児島の出身ですけど、養蚕指導員の父と生け花師範の母は厳しくて、家には「人をうらやましがってはいけません」と墨書きの家訓がぶら下がっていました。18歳で大学進学で上京するや、両親に抑圧されていた好奇心がブレークした。「あたま山」「反対俥(ぐるま)」「そば清」など、荒唐無稽(ことうむけい)で痛快な世界を体ひとつで表現している落語家に感動したんです。「何だこりゃ!」という驚きです。憧(あこが)れて林家木久蔵師匠に弟子入りし、プロの落語家になりました。
カメラも同じ。目と指先を使って、カメラという機械を駆使すると現実の風景を切り取っているはずなのに、その被写体ならでは、その時間ならでは、あるいは撮影者ならではの表現が生まれる。自分の驚きや発見、つまりぼくの「何だこりゃ!」を話芸で表現するのが落語、フィルムに焼き付けて表現するのが写真というわけです。
――寄席の楽屋風景を収めた「楽写」を出版しましたね
楽屋での芸人は素顔です。そこに喜怒哀楽があり、緊張感やリラックスしたしぐさなどがあふれているけど、芸人は楽屋に入った時点で芸人なんです。本には楽屋の見取り図も描きましたが、いろんなルールの中でそれぞれの立ち位置が見えてくる面白さがある。これらの写真は、ぼくの財産です。本を出したおかげで、楽屋口で待っていて写真をくれというファンもできました。(笑)
――撮影はモノクロですね
明と暗の中の芸人の姿を撮りたい。暗い楽屋から明るい高座に出て、また暗い楽屋に戻る。光量の話ですよ、これは(笑)。この明と暗とを行き来する芸人を際立つように写し出すには、背景とか楽屋に置かれている品物などの色はうるさいんです。
レンジファインダーカメラを使うのは、シャッター音が静かで大げさに見えないからです。カメラを構えると、芸人は反射的に顔をつくってしまうので意識されないカメラが楽屋の撮影には向いている。ぼくは、コニカヘキサーを楽屋カメラと呼んでいます。ベッサ-Rもいいですね。ライカM6はロゴを塗りつぶして、大げさに見えないように工夫しています。レンズは標準です。広角だと見えすぎちゃう。落語もしゃべりすぎるとよくない。お客さんに想像して楽しんでもらうのがいいんです。
――故・古今亭志ん朝さんもカメラ好きでしたね
ぼくが楽屋でさりげなくカメラを構えていると、「ふーん、どれくらいかね」と志ん朝師匠が近づいていらっしゃる。思わず、「えーっと、ISO400で、F2の開放です」なんて、ドキドキしながら答えました。それを言うだけで、幸せを感じていました。師匠があるとき、「君、次は何を撮るんだい」とおっしゃるので、「はい、風を撮りたいです」とまじめに答えたら、「おい、ここは笑うところだよ」なんて周りのみんなに声をかけることもありました。
一緒に撮影をしたことはありませんでしたが、「人を撮るときは、どうしているんですか」と尋ねると、「あなたを撮らせてくださいって、きちんと断るんだよ」と言ってから、「でもねぇ……被写体さんに驚かれることがあるんだ」と悩んでいました(笑)。志ん朝師匠がカメラを持って、声をかけてきたら驚きますよね。オリンパスペンFTやコンタックスG1を使われていましたが葬儀のとき、棺(ひつぎ)の上にニコンFM3Aがポンと載せてあった。ああ、志ん朝師匠は最後にFM3Aにたどり着いたのかなと思いました。ぼくは古今亭一門ではないのでカメラを趣味にしていなかったら、志ん朝師匠ほどの大物と話をする機会はなかったでしょうね。
※このインタビューは「アサヒカメラ 2005年4月号」に掲載されたものです

































