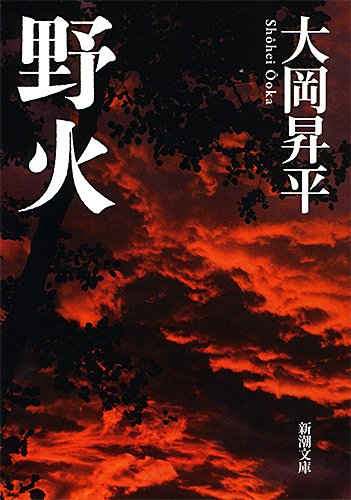
この国はどこへ行こうとしているのか? きな臭さを感じる昨今の日本で、映画監督・塚本晋也が、大岡昇平の戦争文学の傑作「野火」を映画化した。
兵士の腹からザァーッと蛆(うじ)が流れ出る映像を見た瞬間、初めて大岡昇平の小説「野火」を読んだときの衝撃を思い出した。
戦争文学の代表作。フィリピンのレイテ島を舞台に、日本軍から見放された兵士が原野をさまよう。死の直前における人間の極限を描く。
この「野火」を映画化したのは、「鉄男」シリーズや「KOTOKO」など作家性の高い作品で世界中に多くのファンをもつ塚本晋也監督(55)だ。高校生の時に小説を読んで以来、「頭から離れることがなかった」作品を本格的に映画にしようと思ったのが、30歳を過ぎた頃。20年以上を経て完成にこぎ着けた。紆余曲折あったが、「資金集めは大変以前に、どうにもならなかった」と塚本監督。
皆が知っていて自分の大好きな俳優に出演してもらい、スタッフにきちんとギャラを支払う──。普遍的なテーマだし、そのうちできるだろうと思っていた。予算は最低2億円。持ち出しは覚悟していた。ところが、最終的に動き出した3年前に集まった資金は、2億円どころかほとんど0だった。
「10年前から薄々気づいていたんですが、すでに戦争で主人公がぼろぼろになっていく映画にお金を出すという風潮ではまったくなかった。そればかりか、日本が戦争する国に急速に加速している気配が濃密に漂ってきた。作家として20年以上も思ってきた作品を『今つくらねば』という焦りと、このタイミングでお客さんに映画をガツンと打ち当てなければいけないんじゃないかという強い思いがモチベーションになりました」
2005年からフィリピン戦線で実際に戦った元兵士に話を聞いたり、フィリピンで日本人兵士の遺骨収集にも参加したりしながら、主人公田村一等兵の足取りをたどった。資金が集まらないとわかっても、ただ脚本を書き、絵コンテを描いた。自撮りでもいいからやろうと考えた。いよいよ難しくなった3年前は、自分だけでアニメーションで撮ることも検討したほどだ。結局、亡くなった父親の遺産が助けになった。
13年3月27日に大岡昇平の遺族から映画化の許諾を得ると、その日に日本文藝家協会へ足を運び、速攻で動き出した。主演は予算の関係上、最終手段の自分が立つことに。製作・監督・撮影・脚本・編集・美術もすべて自分で担当した。
銃は木を削って、ヘルメットは発泡スチロールで形を作りアルミ箔を貼った。スタッフは飢餓状態の兵士役も兼任。監督は飢餓状態にある田村を演じるため、普段60キロある体重を53キロに落とした。
完成した映画は、「やりたかったことの塊」(塚本監督)だ。人は動物と化し、物体になり果てる。戦争を現実に体験したくないからこそ、映画で悲惨な戦争を追体験し、見る人にも感じてもらいたい。小説でも、田村一等兵は語っている。
「戦争を知らない人間は、半分は子どもである」
※AERA 2015年7月27日号より抜粋





































