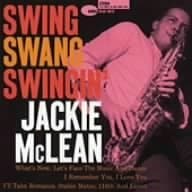
一昔前であったら、ジャッキー・マクリーンをジャズの巨人と言ってしまうことに少しばかりためらいがあった。それはマクリーンを軽んじているのではなく、親しい友人に対して敬語を使うときの躊躇に似た感情だ。私たちジャズ喫茶にたむろす折り紙つきのジャズファンにとっては、マクリーンは日常的にアルバムを聴いて親しむアイドルであって、神棚に祭る存在ではなかった。
だが、それから半世紀近く経った今、彼は相変わらずジャズ喫茶のターンテーブルに乗って私たちを楽しませてくれる一方、確実にジャズ史の一ページに記録されるべきビッグ・ネームの席を占めるに至った。とは言え、彼が何がしかの新たなジャズ・スタイルを創出したというわけではない。そうではなく、ジャズという音楽特有の重要な特徴を、もっともわかりやすい形でファンたちに示し続けてくれた功績によってである。
「個性」、言葉にしてしまえば簡単だが、今ジャズで一番不足しているのが、この個性だろう。私たちがジャズを聴き始めたころ、ジャズという音楽を他のジャンルから分けていたのが「ブラインドという遊びができる音楽」という、一種マニアックな趣向であった。ロックだって十分個性的な音楽だが、《ハード・デイズ・ナイト》は曲目だけでビートルズであることが歴然としてしまう。
だが、ジャズでは、スタンダード・ナンバーをやっている限り、曲だけではミュージシャンを特定することはできない。ましてやアドリブにいたっては、アレンジの特徴で判別することすらままならない。それにもかかわらずジャッキー・マクリーンのソロは、わずかな断片であっても、その音色、フレージング、間の取り方でまず間違いなく彼と言い当てることができた。これは凄いことだと思う。
最近のミュージシャンはみな上手くなったけれど、誰が演奏しているのか非常にわかりにくい。みな似ているのだ。つまりは個性に欠けている。無くなってみて初めて価値に気が付くことがあるが、ジャズにおける個性がまさにそれだろう。マイルス、コルトレーン、パウエル、モンク、皆めちゃくちゃ個性的だったが、彼らの個性は同時に彼らのスタイルでもあった。
ところがジャッキー・マクリーンの演奏スタイルは、大枠をチャーリー・パーカーから受け継いでおり、彼自身が創出した新たなジャズ・スタイルというようなものは特に無い。それにもかかわらず、彼は同じパーカー派アルト奏者たちの誰よりも鮮明に自己を主張している。それもジャズならではのやり方で。
熱に浮かされたような上ずり気味のアルトの音程は、クラシックでは具合悪かろう。せっつかれるようなリズム感はジャズのビッグ・バンドでも、ちょっと問題かもしれない。だが、そうした一般的にはマイナス要因ともみなされかねないものの総体として現れるマクリーン節は、実に心地良く、まさにジャズ以外の何物でもないから不思議なのだ。
とは言え、初めてマクリーンを聴く方たちにあまり味の濃いものをお奨めするのも問題のような気がするので、彼らしさが表れていながら親しみやすいアルバムを推薦しよう。彼以外にホーン奏者のいない「ワンホーン」というのもマクリーンの特徴がわかりやすくてよいだろう。《ホワッツ・ニュー》など、多くのミュージシャンが取り上げたスタンダードからにじみ出るマクリーン節を堪能していただきたい。
ジャッキー・マクリーン:Jackie McLean (allmusic.comへリンクします)
→サックス/1931年5月17日-2006年3月31日
































