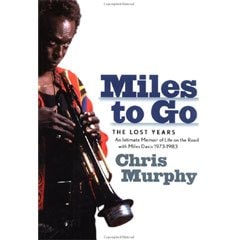
●側近が書いた帝王の知られざる素顔
私は1973年から83年まで(76年から80年まで4年のブランクはあるが)、マイルス・デイヴィスの下で、テクニシャン、ロード・マネージャー、個人秘書を務めた。その間、ツアーに同行して世界をほぼ一周し、数々のおもしろくもあり信じがたい体験をした。マイルスからよく、そうした体験談を書きとめておくよう言われたものだ。
マイルスは、ミュージシャンとして私のヒーローだったが、やがて偉大なアーティスト以上の存在になった。長年、彼と共に過ごし、私はいつのまにかマイルスを一人の人間として愛するようになっていた。私の知る限り、彼のように度肝を抜く人物はいない。マイルスは、神業を地でいくようなものだった。私はそれを目の当たりにして、神のなせる業が実際に存在する、もっとも確かな証拠だと思った。
世間の人は、私とマイルスが親しいことを知ると、口々に二つの疑問を投げかけた。
一つは、「どうして彼のスタッフになれたんだ? 彼は白人が大嫌いじゃなかったのか?」という疑問だった。
もう一つは、「彼は実際どんな人物なんだ?」という疑問だった。
最初の疑問については、「彼は決して白人を嫌悪してはいなかった」と断言できる。第二の疑問については、この本がその解答になる。
マイルスには、よく知られている表向きの顔と公の場では決してみせないもう一つの顔があった。人が笑い転げるほどたまらなくおもしろい一面もあれば、寛大で善意にみちた一面、決して泣き言を言わず、治療法も探らずに長い間、潔く欝と闘った一面もあった。
もちろん、予測できない面もあった。マイルスは、ウィットがあり、並外れて洗練された優雅な紳士になることもあれば、次の瞬間には豹変して粗野で下品なゲス野郎になり下がることもあった。彼は、”タフな”男の例にもれず、乱暴で、痛みに無頓着な外見をつくろい、敏感で繊細な内面を隠した。
マイルスはまた、言葉遣いもユニークだった。そして、言葉のキャッチボールを楽しめる機知に富んだ人物が好きだった。彼はインタヴュアーを楽器のように操り、時にはこと細かに作り話をして、インタヴュアーがマイルスに対して抱いている先入観を煽り、さもなければ時代の反逆児というイメージを増幅させた。
マイルスには実にさまざまな一面があった。私にはわかる。そばにいたのだから。私たちの関係は、単に雇い雇われる以上のものだった。”父と息子”の絆とは言えないまでも、確かにそういう要素があった。私たちは2人で、ボクシングをし、休暇を過ごし、さまざまなことを教えあった。私は一時期、マンハッタン西77丁目の彼のテラスハウスに同居していたことさえある。
そんななか、私はあることに気づいた。それは、マイルス・デイヴィスの実像がわかれば、誰もが彼に惚れこむということだった。彼には人の心を捕らえて放さない魔力があった。私は今もそれを感じている。
本書『マイルス・トゥ・ゴー』は、私がマイルスと共に過ごした日々をふりかえり、喧嘩、女性、スポーツカー、ドラッグや裁判沙汰について語りながらも、音楽、人種差別、名声や独り歩きする虚像をテーマにしている。そして、マイルスが経験したアーティスティックな葛藤や肉体的精神的な苦闘をあきらかにする。
彼はファイターだった。求愛者でもあった。彼自身のアートに関してもセックス・ライフに関しても、常に新しく違うものを探し出した。過去は彼にとって退屈きわまりないものだった。
さあ、黒人のアメリカン・ヒーローのエピソードを、幸運にも彼の仲間に加わることができた白人の若者の視点によるアメリカン・ストーリーを伝えることにしよう。(著者の言葉より)


































