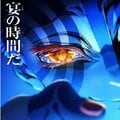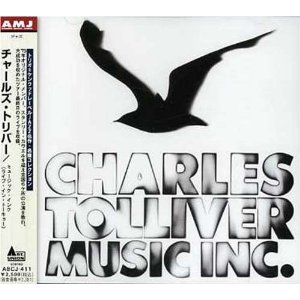
Music Inc. / Charles Tolliver (AMJ [Trio])
1973年、ジャズ・ミュージシャンの来日は1964年以来のラッシュとなる。純ジャズの範囲で見てもスウィングの巨人、テディ・ウィルソン(ピアノ)から前衛の闘将、セシル・テイラー(ピアノ)まで、さらに準ジャズに広げるとジョン・マクラフリン(ギター)の「マハヴィシュヌ・オーケストラ」やガトー・バルビエリ(テナー)らが来日、ジャズのテーマパークの様相を呈した。純ジャズ系で新風を感じさせたグループといえば年明けに来日したチック・コリア(ピアノ)率いる「リターン・トゥ・フォーエヴァー」と棹尾をかざったチャールズ・トリヴァー(トランペット)-スタンリー・カウエル(ピアノ)の双頭クァルテット「ミュージック・インク」だろう。もっとも反響がジャズ外にも及んだ前者には「ジャズではない」という保守的な意見も少なくなかったから、大方のジャズ・ファンから好意的に迎えられたのは先進性と燃焼力を兼ね備えた後者だったと記憶する。
トリヴァーが頭角を現したのは1960年代の後半、ジャッキー・マクリーン(アルト)やホレス・シルヴァー(ピアノ)のグループに起用されてからだが、個人的に注目したのはカウエルと組んだリーダー作『ザ・リンガー』(1969年6月/Polydor)からで、まさに彗星のように現れたという印象だった。その演奏は1960年代の成果たるモードや変拍子にブラック・パワー華やかなりし1970年前後の熱気をブチ込んだ感があり、いまだ「政治の季節」の余燼が燻ぶっていた気分に見合ったのではないかと思う。筆者もまた来日公演や東京FM系で放送されたライヴ録音にふれて感激し、のちにトリオから本作が発表されると真っ先に飛び付いた口だ。しかし、トリヴァーが1970年代の後半に早々と失速する頃には関心を失くしていた。あれは余燼の燻ぶりによる熱病だったのか、関心を失くしたのにはそれなりの理由があったのか、絶頂期の記録である本作に答えが見つかるかもしれない。
グループはトリヴァー、カウエル、クリント・ヒューストン(ベース)、クリフォード・バーバロ(ドラムス)という顔ぶれで、11月29日から12月7日まで7公演をこなした。本作には最終日の東京公演の一部が収録されている。オープナーは《ドラウト》、モロにモーダルなフレーズをルバートでひとしきり、その当時はこのコルトレーン風の導入部に魅かれたのだろう。やがてファストに転じるとカウエルは抜け中盤まで機銃掃射で独走、クリシェを避ける姿勢は買うが、ときに脈絡を欠き、ときに単調になるのは感心しない。中盤から主役に立つカウエルはさすがのセンスを見せて膝を打たせる。終盤のドラムス・ソロは力感も芸もなくタダの時間稼ぎだ。ベースの刻むキャッチーなイントロに導かれる《ストレッチ》は前半はテクニカルなベース・ソロで占められる。後半から主役を務めるトリヴァーは肩の力が抜けて適度にエモーショナル、親しみ易くもあり好ましい出来だ。
《トゥルース》は珍しくもリリカルなスロウ・バラードで、トリヴァーが主役を張る。抑制の効いた佳演だ。《エフィ》はカウエルの作曲の才が知れるキャッチーなメロディのジャズ・ワルツで、前半はカウエルが主役、後半はヒューストンが《ストレッチ》を凌ぐテクニカルなソロを繰り広げて凄い。これも珍しいが、モンクの《ラウンド・アバウト・ミッドナイト》ではカウエルだけを伴った序盤のルバートからトップ・スピードに転じて再びルバートに戻る終盤までお馴染みのメロディは断片すら現れない。高速テンポといい斬新な和声付けといいトリヴァーならではだが、同曲にする必然性があったのか疑問だ。おそらくトリヴァーの延長線上にはウィントン・マルサリスがいる。違いは黒人としての体温差で、クールな資質と、ときに難しいことを難しく響かせる性癖は共通すると思う。そこらが鼻についたらしい。ともあれ、短い絶頂期の雄姿をとらえた貴重な好ライヴだ。
【収録曲一覧】
1. Drought
2. Stretch
3. Truth
4. Effi - Round About Midnight
Charles Tolliver (tp), Stanley Cowell (p), Clint Houston (b), Clifford Barbaro (ds)
Recorded At Tokyo Yubin Chokin Hall, Tokyo, December 7, 1973