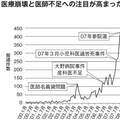「幼少期の舛添氏は他の子どもが持っているようなおもちゃを買ってもらえなかった。いつも一本の『肥後守』(ナイフ)を持っていて、それで木を削って、おもちゃを自作していたという。舛添氏は今もナイフの収集が趣味だといいますが、このときの原体験が影響しているのかもしれません」
この関係者に対し、舛添氏は以前、自らの頭を指さし、「自分はここ(頭)を使うしかなかったんだよ」と語ったという。その言葉どおり、苦労人は勉学一本でのし上がった。
東大法学部を卒業後は助手として学者の道を歩み始めるが、73年に独断で渡仏し、パリ大学やジュネーブ高等国際政治研究所に客員研究員として5年間留学。79年に帰国後は東大助教授となり、6カ国語を操る気鋭の国際政治学者としてメディアで注目されるようになる。89年には母校を「さらば東大のアホどもよ」などと激しく批判し、辞表を提出。在野の学者に転じた。教授職の後継者争いに敗れたことが遠因だった、との見方もある。
「故郷でも東大でもはぐれ者だった舛添氏にとって、パリやロンドンなどのヨーロッパこそが精神的な故郷。豪華な視察旅行でそこを訪れることこそ、“故郷に錦を飾る”行為だったのかもしれません」(前出の関係者)
華麗な経歴に隠された苦節の時代が、特異な金銭感覚の原点なのだろうか。
※週刊朝日 2016年6月3日号
こちらの記事もおすすめ 舛添都知事疑惑まとめ クレヨンしんちゃん400円、喫茶店代1万8千円…