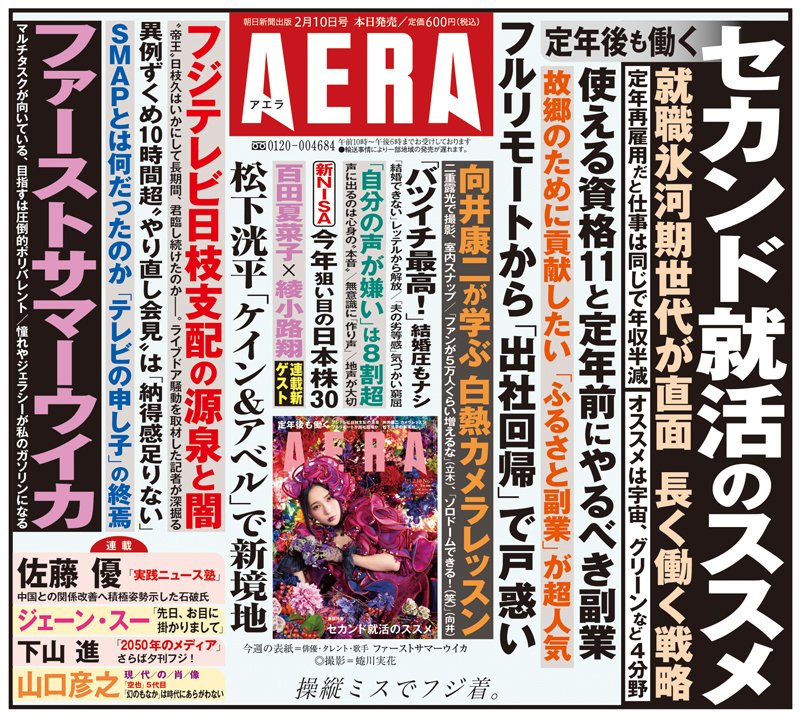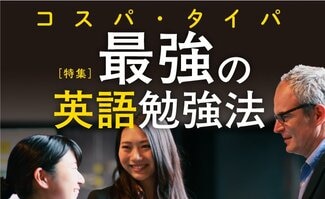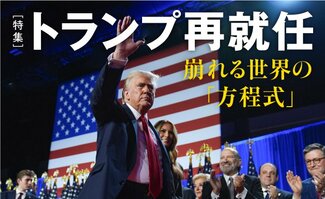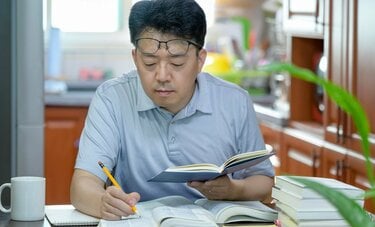■来日作「エマオの晩餐」の見どころ
復活したイエスが、エルサレム近郊の町エマオに向かう弟子の前に現れたという、新約聖書の一場面を描いた作品。左から2人目がイエス、座っている二人が弟子、立っているのは宿の主人夫妻です。
宗教画でありながら、どこか倹(つま)しい一般家庭の光景のように見えませんか? もっと崇高に描くべきキリストの復活を、庶民的次元で捉えた、日常性がポイントです。ここまで緻密で豊かな表情の人間を描いたのは、カラヴァッジョが画家として初めてだと思います。
ちなみにこの作品は、ロンドンのナショナル・ギャラリーに所蔵されている作品(1600-01年)と同テーマで1606年に描いたもの。人物の配置が換わり、女性が加えられました。再度描いた理由は知られていませんが、気持ちはわかりますよ。私も、自分の漫画作品でいずれ描き直したいと思うものがありますから。自分の画力も変わりますし、テーマはとてもいいのだから、時代を照らしあわせて、いまこの感情で描いたらもっといい絵になる、と思ってしまうのが、絵描きの性ではないでしょうか。
見どころはやはり、特徴的な黒い背景と光の使い方。
カラヴァッジョ作品のほとんどは、背景がべったりと黒く塗られています。真っ黒にすることで、リアルさが増し、人間の本質も浮き彫りになる。漫画家で言うと、つげ義春さんの“ベタ使い”に似ています。「黒」というものは何もかも吸い込んでしまうような力をもっているし、癒やしを求める人びとの気持ちに優しく働きかけてくれる色でもない。「黒」は使う作家にとっても怖い色ですから、現代でも、なかなかこんな闇の表現をできる漫画家はいないと思います。
カラヴァッジョの場合は、その黒を駆使した光の当たり方、陰影の濃さがとても映像的です。それ以前の、記号化された描き方を無視して、暗くて見えないところは見えないままでいい、としたカラヴァッジョの恐れ知らずな革新性は素晴らしい。この光の使い方は、多くの影響を受けたカラヴァジェスキたちを経て、のちのレンブラントへとつながっていくのでしょう。
■カラヴァッジョ展
6月12日(日)まで
国立西洋美術館(東京都台東区上野公園7-7)
http://caravaggio.jp
ヤマザキマリ
1967年東京都生まれ。84年、17歳で単身イタリアに渡り、国立フィレンツェ・アカデミア美術学院で、美術史と油絵を学ぶ。97年漫画家デビュー。古代ローマの浴場設計技師を主人公に描いた「テルマエ・ロマエ」が空前のヒットとなり、2010年、マンガ大賞、手塚治虫文化賞短編賞を受賞。ほか漫画作品に『プリニウス』(とり・みきと共著)、『スティーブ・ジョブズ』など、著書に『ヤマザキマリのリスボン日記』『国境のない生き方』『ヤマザキマリの偏愛ルネサンス美術論』などがある
※週刊朝日 2016年3月11日号に加筆修正