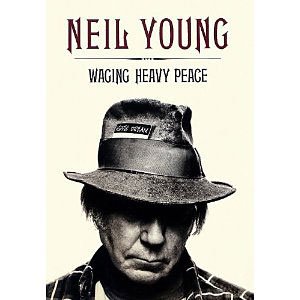

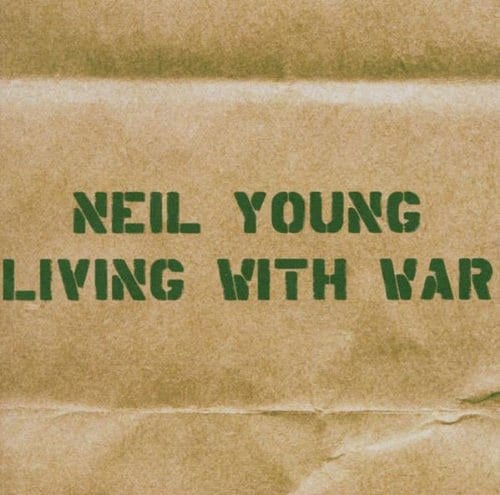
何年に一度かわからないが、忘れたころに、思わず涙がこみ上げてくるような音楽と出会うことがある。これを「こみ上げ盤」と呼ぶことにするが、ぼくにとっていまのところ最後の「こみ上げ盤」は、ニール・ヤングの『リヴィング・ウイズ・ウォー』というアルバムになる。発売された年をみると2006年。もう7年も経ったのか。
ぼくはこのアルバムが、ニール・ヤングのファンやいわゆるロック・ファンとかその周辺でどう評価されているのか知らないが、傑作だと思う。とくに《ファミリーズ》という曲から最後の《アメリカ・ザ・ビューティフル》にかけて連続して収録されている6曲は名作の連なりで、それは雄大な山脈や寄せては返す大海の大波を連想させる。
そういう流れで聴いていくと(それまでの曲や流れが悪いというわけではないが)、2番目に《フラッグス・オブ・フリーダム》という曲が流れてくる。訳せば「自由の旗」ということになるが、この場合の「旗」はアメリカ国旗を指している。これがじつにいいのですね。60年代大好きオヤジやあの時代から逃れられない人には、絶対にお勧めします。とくに歌詞の、
「Listenin' to Bob Dylan singin' in 1963」
「Flags that line old Main Street / Are blowin' in the wind」
という部分になってくると、ぼくはいつも泣きそうになる。ここもまた、この「こみ上げ盤」のクライマックスのひとつなのです。それに追い打ちをかけるようにニール・ヤングが吹くハーモニカも。
『ニール・ヤング自伝』(奥田裕士訳:白夜書房)を読んだ。上下の2巻に分かれ、それなりに分厚いが、文字がやや大きく、文字数的には「ちょっと分厚い一冊分」といったところだろうか。原書は一冊だが、それを上下に分けて出したところがミソで、作戦勝ちという感じがある。
内容的には、まあこのようなものなのだろう。スキャンダラスな話題もなく、新しい発見のようなものもそれほどない。むしろ淡々と綴られている。ニール・ヤングも68歳、過去はすべて美しい思い出になったということだろうか。とはいえニール・ヤングが老いたということではなく、それは新作を聴いてもわかるが、まだバッファロー・スプリングフィールドのメンバーのように若い。
ぼくが最も興味をもったのは、ニール・ヤングがどのようにこの本を書いたのかという方法論だった。それはぼくが書くことを仕事としているということと関連しているのかもしれないが、はたしてニール・ヤングは、この分厚い本をどうやって書いたのか。
この本は、ボブ・ディランの自伝がそうだったように、時系列で順を追ってこれまでの人生と出来事を書いたものではない。むしろあっちに飛び、こっちに飛びで、注意深く読まないと置いてけぼりを食らうことにもなりかねない。さりとて時空を超えた超常現象的かつ幻想的な展開というものでもなく、トーン(ここでは「音質」と訳したい)というか色彩感は、どことなく統一されたものになっている。それはそうだろう、同じ人間がずっと書いたのだから。いやそういうことではなく、これは構成によるものだと思うのだ、ぼくは。
おそらく、そう、おそらくという推論をたぶんに含んだ「読み」ではあるのだけれど、おそらくニール・ヤングは、最初から最後まで、律儀に時系列に書き上げていったのではないだろうか。そして一度は完成させ(ニール・ヤングには、どうも「脱稿」という言葉は似合わない)、それを68の章に切り刻み、次いで前後を入れ替え、そうして再構成することによってこの自伝というか物語を構築したのではないだろうか。
そう考えると、下巻の第60章からエンディングに向かっての盛り上がりと感動の秘密が理解できるような気がする。つまりこの部分は、書かれた内容というよりは、構成上の工夫と演出によって成された、ニール・ヤングの力技(チカラワザ)なのではないか。
そういうふうに見てみると、ものすごく当たり前のことに気づく。ニール・ヤングはこの自伝を、映画のように、音楽のように組み立てることを思いついたのだろう。そしてぼくが自伝を読んで受けた最初の印象は、ニール・ヤングの音楽を聴いたときの印象とほとんど変わらなかった。それはニール・ヤングの音楽が、あるいは楽曲や主なアルバムが、(おそらくは)そのような手法や発想でつくられているからにほかならない。
この自伝は、だからだろう、読んでいると、まるで音楽に身を預けているような気分になる。そして強烈にニール・ヤングの存在を感じ、懐かしい親しい気持ちが芽生えてくる。しかもニール・ヤングとの距離はけっこう近い。先に内容的に不満めいたことを書いたが、思うにミュージシャンが自分で書いた本というものは、自伝であれなんであれ、このように読者に思わせた者が「勝ち」なのではないだろうか。そこに「ミュージシャンが自分で書くことの意味」があるように思う。
その意味で、ニール・ヤングは、生涯で一冊しか書けない立派な自伝を書いた。さあ、もう一度『リヴィング・ウイズ・ウォー』を聴こう。あっ、ちょっと待てよ、久しぶりに『ハーヴェスト』か『渚にて』にしようか。いや、やっぱりいちばん新しい『サイケデリック・ピル』にしよう。
































