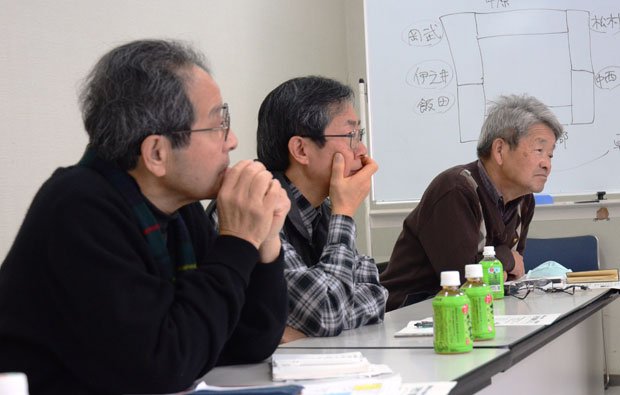
最近、男性が「主な介護者」になるケースが増えている。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2001年の23.6%に対し、13年は31.3%(同居の場合)。3人に1人弱が男性という計算になる。
フリー編集者のDさん(51)は2年前、パーキンソン病を患う父(84)を世話してきた母(74)が体調を崩したのを機に、約30年暮らした東京を離れて、関西の実家へ帰った。
同居して以降、母は元気になったが、父は悪くなるばかり。近くに住む妹は3人の子育てに追われ、頼りにならない。父は粗相し、しょっちゅう転倒する。母一人ではとても起き上がらせられない。地元に親しい友人はなく、孤独が募る。
関西には出版社が少なく、仕事は激減し、収入は半分以下に。近ごろはタクシーの運転手なら雇ってもらえるかと、本気で考えた。
「サラリーマンで安定した収入があれば父を施設に入れられた。でも今の自分には無理。将来の展望はなく、考えたくもない」
予備校講師で独身の上村聡さん(57)は17年前、今は亡き父が脳梗塞などで重い後遺症が残り、母の手には負えないと感じて両親と同居を始めた。父は思うように体が動かぬいらつきから毎夜、罵詈雑言を発した。ショートステイを利用しようとすると、「暴れて預かれない」と追い返された。
「何度も父を殺そうと思い、自分も死にたかった。当時も仕事は続けていたが、記憶がすっぽり抜け落ちています」
職場では「あの人は介護で大変だから」と飲み会や親睦旅行に誘われなくなった。一生の趣味のはずのオーケストラを退団し、ピアノも売った。いま要介護2の母(88)を介護しながら、その束縛に苦しむ。
殺意さえ覚えるほどの過酷な家族介護の現実がある。
今年2月発売の『迫りくる「息子介護」の時代』の著者で、東京都健康長寿医療センター研究員の平山亮さんによると、男性は介護に対する問題意識が希薄で、親の健康状態を軽く見てしまう傾向があることが海外の調査でも報告されているという。
「娘ならすぐに気が付く異状にも、息子は『年を取れば、そんなもの』と思い込んで必要なケアをせず、症状を進行させてしまう。同居の息子がいるのに近所の女性が認知症に気付いた例も珍しくありません」
そこで求められるのはまず、介護する男性が独りで抱え込まず、オープンにすることだ。とりわけ職場は、社会の接点にもなり得る。
企業のワークライフバランスを支援する民間会社「wiwiw(ウィウィ)」の山極清子社長がかつて支援した企業では、全社員に「あなたは今後5年のうちに介護を担う可能性があるか」と聞いたところ、8割がイエスと答えた。待ったなしの状況だ。
「これは決して極端な例ではなく、どの企業が直面してもおかしくない。貴重な人材が介護と仕事と両立できずに大量離職する恐れがあるにもかかわらず、仕事に全力投球できない社員は邪魔と考えるところさえあるんです」
取材から見えたのは、介護する男性は実はたくさんいることだ。山極さんは「黙っていては何も変わらない。社内でも声を上げればきっと同じような状況にある人が見つかる」とアドバイスする。
「介護も仕事と同じで、自分でやるべきことと人に任せられることがある。仕事で培ったマネジメント力を生かして家族や介護従事者とプロジェクトを組み、休暇はその段取りを整えるのに使う。いかに介護支援サービス等を積極利用できるかが、離職防止の秘訣です」
※週刊朝日 2014年9月5日号より抜粋









































