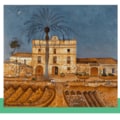10月12日に行われたサッカー日本代表対パナマ戦。その85分、中央でドリブルを仕掛ける原口元気からペナルティエリアでパスを受けた川又堅碁にGKホセ・カルデロンが迫ると、後ろからDFマイケル・ムリジョがチャージしてきた。バランスを崩しながらボールを捉えに行く川又は、さらにGKとの接触で前のめりになって倒れこむが、ボールはそのまま転々とゴールラインを割った。
テレビ実況は「川又らしい気持ちで押し込んだゴール」と叫んでいたが、その後の判定で公式記録はオウンゴールとなった。「シュートを打とうとしたらたぶん相手の足を蹴って、相手の足がそのままボールに当たってゴールになった。スパッと決めたら、もうちょっとカッコ良かったけど」と川又。それでも「(代表で)点に絡むことはなかったので、それはよかったですけど」と振り返る。
パナマのガリー・ステンペル監督も「馬鹿げた形で3点目が入った」と悔やんだが、ゴールはゴールだ。同じ途中出場の北川航也とクロスオーバーで飛び出したところから、原口のパスにピタリと合わせられれば、後ろからチャージされる前にシュートできていたかもしれない。だが、こういうシチュエーションにおける球際の強さというのはストライカーにとって大事な要素の1つだ。
とりわけ、代表戦というのはギリギリのところで勝負が決まってくる。“決定力”にはフィニッシュのイマジネーション、相手との駆け引き、味方との呼吸、瞬間的な空間認識力、シュート技術など総合的な能力が結果として表れるものだが、相手のディフェンスがいる以上はレベルの高い試合になるほどゴール前の隙は小なくなり、いわゆる“球際の強さ”も求められてくる。
そうした状況でゴールが決まるとよく「気持ちで押し込んだ」と言われるが、まず大事なのはそうしたところに飛び込んでいける判断力と運動能力だ。その上でコンマ何秒、何センチといったところの勝負をものにするのはゴールへの執着心。“気持ち”だけではそういうシチュエーションすら生まれないが、五分五分のところでも可能性を信じて飛び込んでいく、いざ相手に阻まれても諦めずに食らいつくといったところが勝敗を分ける。