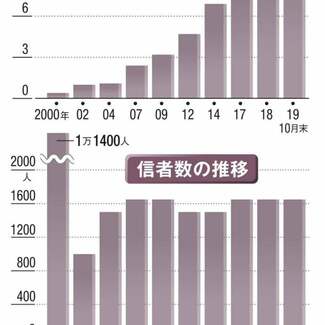──新約聖書のヨハネの黙示録で悪霊が神と戦う地とされるハルマゲドンを、オウムは最終戦争を表す言葉に歪めて信者の危機感を煽りました。
「ハルマゲドンとか救世主とか、麻原一人が言っただけなら反応しなかったと思うんです。これは責任回避と受けとめないで欲しいのですが、社会がお膳立てしてくれた上に登場したのが麻原だった。以前から欲しいと思っていたものを、『それはオレだ』と麻原が言ってくれたような感じで……」
あとから考えれば馬鹿げたことだと一蹴できても、渦中では認識できないことがあり、当時は確かに上祐の語るような風潮をメディアも煽っていた。いまだって似たようなところはあるが、大ベストセラーとなった作家・五島勉の『ノストラダムスの大予言』はその筆頭であったし、多くの雑誌やテレビ番組も「超常現象」やら「超能力」やら「霊感」やら、あるいは「風水」「占い」「血液型」といったエセ科学に公然と市民権を与えていた。
そう、犯罪や事件といったものは時代と社会の歪みを時に見事なほど映し出す。言葉を換えれば、犯罪や事件には時代や社会の臭いがべったりと張りついている。エセ科学や世紀末の社会風潮が駆動力のひとつとなったオウム真理教というカルト教団について言えば、麻原こと松本智津夫が前身のオウム神仙の会を創設したのは1984(昭和59)年。それから地下鉄サリン事件を引き起こすまでの約10年間は、いわゆるバブル景気に日本全体が踊った時代とも重なり合う。
街に札束が乱舞し、一見したところ華美で豪奢な時代状況にも背を向け、若者たちはオウムに吸い寄せられた。学生の就職は未曽有の売り手市場に沸き、若い女性たちはボディコン姿で繁華街を闊歩していたというのに。
再び上祐の回想である。
「例えて言うと、(オウムには)霊的ベンチャー企業のような側面がありました。比較的小さなカルト的教団なら、エリートがすぐトップに行ける。中堅のベンチャーが東大や早大から人材を引き抜き、すぐに部長や専務をやらせると言ったら入社する者もいるでしょう。また、経済的なバブルに慢心した多くの日本人と同様、精神世界に惹かれた者にも慢心があったんです」
 青木理
青木理