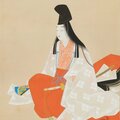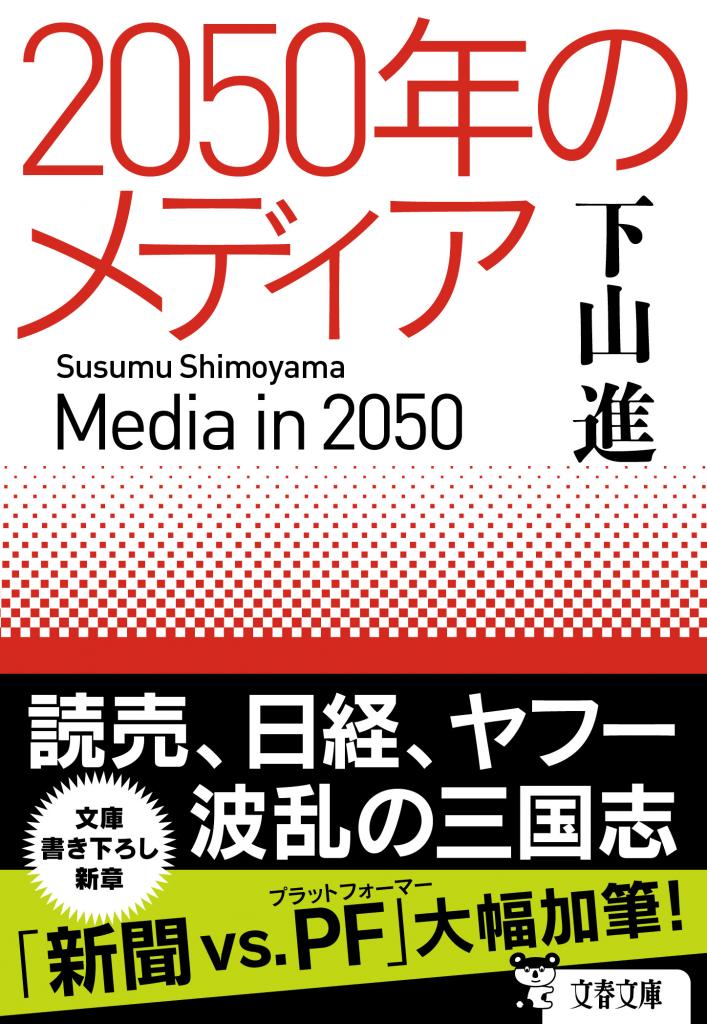
このコラムのタイトル『2050年のメディア』は、2019年10月に刊行された単行本からとっている。その文庫版が文藝春秋より刊行された。
この文庫版には、400字×70枚の書き下ろしの新章「新聞vs.プラットフォーマー」が加わっている。
インターネットの登場で何がかわったかと言えば、メディアのゲートキーパーともいうべきプラットフォーマーが成立していったことだ。グーグルやフェイスブック、アップルなどはそれぞれプラットフォーマーになることで、競争他社を淘汰し、独占的地位を確立していった。
日本では1996年に創業したヤフーということになるだろう。これがいかに巨大な存在かということは、月間のPV数を見ればたちどころに了解できる。そのPV数は200億PV以上。ニュースサイトで言えば話題になっている文春オンラインでも、最新の数字で3億7000万PVだから、いかに多くの人々がヤフーに集まっているかがわかるだろう。
そうした吸引力のあるサイトには、ニュース配信料が安くとも報道機関はコンテンツを出したがる。現在300媒体以上が、ヤフーにニュースを提供している。
むろん、一朝一夕にそうした存在になったわけではない。1990年代後半には住友商事のやっていたライコスやNTTが始めたグーなどの大手が始めたサイトが乱立しており、当時1000億円程度の売上しかなかったソフトバンクの始めたヤフーは、そのうちのひとつにすぎなかった。それが他社を引き離しプラットフォーマーに成長していくのに、8本の旬のニュースを次々に掲示していくヤフーニューストピックス(ヤフトピ)が大きな力を持ったことは論をまたない。
そしていったんプラットフォーマーが成立すると新規参入は容易にしづらい状況になる。
次の新しい技術革新があるまでは──。
その技術革新は、2010年に始まった4Gと呼ばれる第四世代の通信規格だった。これによって動画や音楽が、無線で瞬時に送れるようになった。そうするとPCから、スマートフォンへの人々の移行が始まる。2010年には9.7パーセントだったスマートフォンの普及率は、2017年には75パーセントに達する。