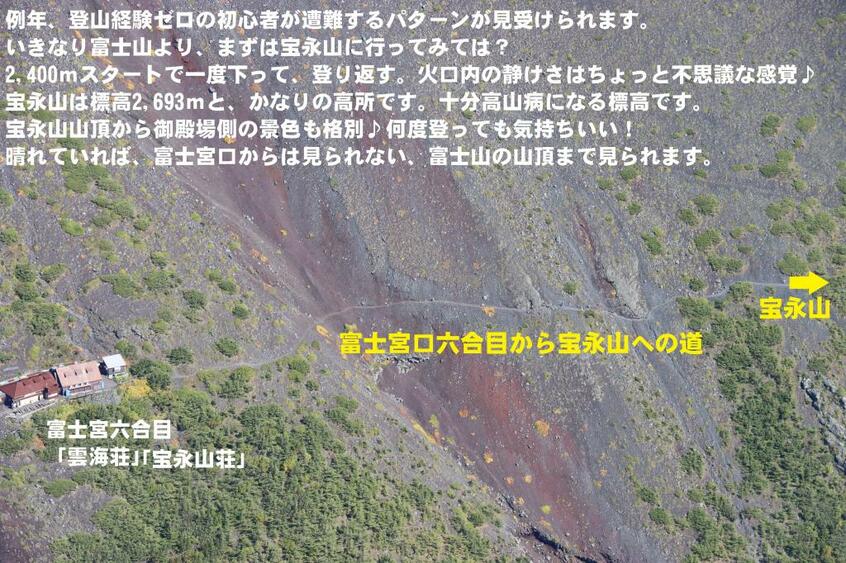
「よく、『山をあまく見ていた』『まったく運動もせずに来て、足がつっちゃった』などと、言われる方もいます。ほかにも『疲れて動けない』『足がもつれて転倒した』『道を間違えたが、もう登り返せない』とか、そんな遭難が多いんです。要するに、疲れ果ててしまって、下山するための体力が残っていない。そこで救助を要請される」
富士山はほかの山と比べて特に標高が高いため、高山病を発症し、助けを求める登山者も少なくないという。
「高山病の症状は登れば登るほどひどくなります。高山病にかかったら、即、下山して高度を下げることが必要です」
昨年の富士登山者はコロナ前の3割ほどだったが、今年は登山者が増え、遭難者数も増えると予想される。
「富士山だからと侮らず、きちんと事前の準備をしてほしい。登山計画を立て、自分の体力に合った登山道を選び、休息場所や山小屋の位置をつかみ、下山ルートも確認する。時間的にも無理のない登山をお願いしたい。体力強化にも励んでいただきたいです」
静岡県警地域課はTwitterでさまざまな実践的アドバイスを発信しているので、参考にしてほしい。
■“本格登山”の北アルプスでも
北アルプスはどうだろうか?
意外なことに、富士山よりも本格的な登山者が訪れる北アルプスでも「準備不足」「体力不足」が原因の遭難が目立って増えているという。
長野県警山岳遭難救助隊の岸本俊朗隊長はこう語る。
「『バテてしまって、もう動けません』とか、日没後『ヘッドライトがないので帰れません』とか。そういった遭難が非常に増えています。山岳遭難の統計上、それは『無事救助』に分類されるのですが、これが昨年、初めて4割を超えました」
「無事救助」の場合、登山者本人の心がけ次第で防げた遭難がほとんどである。
「登山って、マラソンと同じくらい負荷がかかる激しいスポーツなんですが、実際には観光や旅行の延長みたいにとらえている方が多い印象を受けます。あまり体力がない方や、きちんとトレーニングをしていない方が増えている」





































