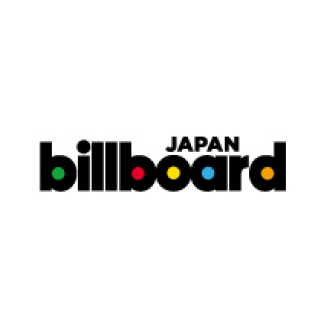つい先日の日本公演でも喝采を浴びたルノー・カピュソンの新譜は、今をときめくフランソワ=グザヴィエ・ロト率いるロンドン交響楽団を従えての、バルトークの2つのヴァイオリン協奏曲である。特に近現代の分厚いレパートリーを誇るカピュソンだけに、待ち望まれたアルバムと言えるだろう。
死後だいぶ経って発見された第1番は、まだ26歳の頃、1907年から翌年にかけて書かれた作品で、ヴァイオリニストのシュテフィ・ガイエルとの情熱的な恋を色濃く反映した2楽章形式の作品だ。最初の4つの音がガイエルの「ライトモティーフ」だ、と彼女との別離の後に書き送っているように、この音素材が2つの楽章に散らされている。
嘆き歌のような音楽が紡がれる第1楽章は独奏ヴァイオリンから入るため、ヴァイオリニストの奏でる、この「ライトモティーフ」の音色いかんでほとんど勝負は決まってしまうのだが、カピュソンならではの甘いトーンの引力は十二分にその要請に応えている。
やがて弦楽器、ついで木管が入り、徐々に独奏ヴァイオリンに寄り添う楽器が増えてゆくが、ロトのタクトは明晰で曇りがなく、物憂げでロマンティックとすら言えるこの楽章を盛り立てている。一転して躍動感のある第2楽章ではヴィルトゥオーゾ的パッセージが際立つが、対照的な抒情的なパッセージとのコントラストが効いており、耳に心地よい。
第1協奏曲の作曲から30年が経過した1937年から翌年に書かれた第2協奏曲は、作曲家として揺るぎない評価を得た成熟期の作品である。
ハンガリー民族音楽の色濃い影響が窺える第1楽章冒頭から、やがてモーダルな音楽にも12音技法にも接近してゆくが、カピュソンとロトのアプローチは、たとえば抒情的な第2主題群ではたっぷりと歌わせつつ、技巧的なパッセージは颯爽と駆け抜ける、といった具合に、第1協奏曲第2楽章に輪を掛けてメリハリをつけたものになっている。カピュソンは、特にこうした歌心と超絶技巧の共存バランス感覚に優れた奏者ということもあって、そうした処理はお手の物、ロトとの息もピッタリと合っている。
変奏曲形式の第2楽章では、胸を抉る旋律を詩情豊かに彩っている。楽章全体において独奏ヴァイオリンが主導的立場を担う変奏曲だけに、その存在感が試される楽章だが、カピュソンは積極的に音楽を牽引している。第2変奏ではこの楽章で活躍するハープとの対話が活発だし、第5変奏スケルツァンドはこの上なく軽やかで茶目っ気も効いている。第1楽章の自由な変奏になっている第3楽章は闊達で隙がなく、展開部の優美さなど格別だ。
いずれの協奏曲も、カピュソンの音色美と確かな技巧に裏打ちされたソロの魅力が花開いているとともにロトのサポートも万全、見事な演奏である。Text:川田朔也
◎リリース情報
ルノー・カプソン『ヴァイオリン協奏曲第2番、第1番』
WPCS13761 2,808円(tax in.)