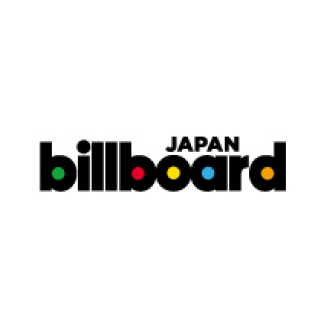風が冷たく感じられるようになった晩秋。ボズ・スキャッグスの歌を聴くのにもっともふさわしい季節かもしれない。お客さんの年齢層は50代が中心だろうか。幅広い人気と、高い音楽性の両方を兼ね備えた人だけに、客層も豊かだ。70年代後半から80年代にかけての青春期を、彼の音楽を聴きながら過ごしたであろう雰囲気の人たちが、硬軟両派とりまぜて揃っている印象。そうだよなあ、棲み分けや細分化が進む前の、それもヒット曲を何曲も持っている人気シンガーって、こういう風に聴かれてたんだよなという気がする。
定刻を5分過ぎ、メンバーにつづいてステージに現れたボズが“Nagoya?”と一言。ちがうよー、ここは大阪だよー、という客席の反応に特に悪びれた風もなくギターを肩にかける。クールにミディアムビートを刻む「Jojo」で、ライブはスタートした。
一曲終えて、“Thank you, Osaka.”と笑顔を見せ、“さっきのジョークを許してくれるかい?” と話すボズ。真顔で冗談を言うこの感じ、媚びる様子は微塵もないのだがサービスも怠りないという態度は、彼の音楽にもどこか通じているようだ。
オープニングはヒットソングで始まったが、ここからは、今年初めにリリースした5年ぶりのニューアルバム『Memphis』からのセット。ボズ自身の音楽的ルーツである、ソウルやリズム&ブルースへの敬愛の念をたっぷり盛り込んだこのアルバムから、まずは「Mixed Up,Shook Up Girl」を。
これは、ブロンディやテレヴィジョンと同時期に、ニューヨークのライブハウスCBGBのステージに立っていたニューヨークパンクの一派、ミンク・デヴィルのカバー。といってもこのバンド、実はルーツロック志向が強く、フロント・マンのウィリー・デヴィルは、後年、ニューオリンズを中心に活動していた。ウィリーは4年前に癌でこの世を去ったが、ボズの南部色豊かなカバーバージョンを聴けば、天国でニヤリとするんじゃないだろうか。
つづいては、著名なトランペット奏者でもあるジャック・ウォルラスが書いたブルースナンバー「Dry Spell」。アルバムでは、ケブ・モが披露していたスライドギターを、ここでもしっかり聴かせてくれる。
次に、椅子に腰かけたボズが、ギターをアコースティックに持ち替えて歌ったのは、雨だれのようなピアノも美しい「Rainy Night in Georgia」。トニー・ジョー・ホワイトの作曲とブルック・ベントンの歌唱であまりにも有名なこの曲につづいては、オールド・フォークソング、「Corrina, Corrina」。そして、この『Memphis』パートは、アルバム冒頭を飾っているボズのオリジナル曲「Gone Baby Gone」で一区切り。
後半に入り、イントロから歓声の上がった「Georgia」では、後半のサビのファルセットもよく出ている。69歳という年齢、にわかには信じ難い。
その都度、誰が書いた曲なのかを語りながら進行しているボズが、今度は“マイフレンド、デヴィッド・ペイチが書いた曲”と紹介した。ボズのバックを務め、のちにそのメンバーでTOTOを組むことになるペイチが'77年には書き上げていた曲で、ボズのレパートリーとしては'80年に発表したベスト集『Hits!』のボーナストラックとしてレコーディングされた「Miss Sun」である。
オリジナルバージョンでは、カナダ出身の女性シンガー、リサ・ダル・ベロが相手役を務めていたが、今回のステージでは、アルバム『Memphis』にも参加していた女性コーラス、モネ・オーウェンズとの掛け合いで聴かせる。これが非常に楽しいものになっていて、ステージはそのまま、モネの独壇場がつづく。ファンキーママとでも呼びたくなるような貫禄のボイスでスライ&ザ・ファミリー・ストーンの「Thank You」を歌い、観客を煽りまくるモネ。ハンドクラップを求め、1階のお客さんのほとんどを立ち上がらせてしまった。
興奮が駆け抜けた客席の熱をクールダウンするかのように、今度は物憂げなキーボードの音色が流れてくる。「Harbor Lights」だ。本篇も大詰め、ここはボズの代名詞的存在でもある大ヒット作『Silk Degrees』からの連発である。「Lowdown」では大きな手拍子で、そして「Lido Shuffle」では総立ちで喝采を送る客席。ヒートアップして本篇は終了した。
アンコールに応えて登場し、『Silk Degrees』の1曲目だった「What I Can Say」でメンバー紹介をすると、今日初めてギターを置き、手ぶらでスタンドマイクの前に立つボズ。歌いだしたのは「We Are All Alone」。後ろの席の女性客が、しきりに“感動や、感動や”とつぶやいている。それだけ、有無をいわせない名曲ということか。
さらに、'97年に発表したR&Bアルバムから、“Very special love song.”と歌い出したのが「Sick & Tired」。ファッツ・ドミノのヒットでも知られたこの曲を、先達に忠実な叩きつけるようなピアノプレイとオールドタイムなサックスソロを交えて御機嫌に披露する姿は、ただのR&B好きのティーンエイジャーに還ったかのようでもある。
ラストは、今年6月にメンフィスで83年の生涯を閉じたブルース・シンガー、ボビー"ブルー"ブランドの名を挙げながらプレイするブルースの大作、「Loan Me A Dime」(作者は、"メロウ・ブルース・ジニアス"の異名を取ったフェントン・ロビンソン)。'69年に、ボズが自身のソロデビュー作に収録したときのテイクでは、当時まだ無名だったデュアン・オールマンが参加して鮮烈なスライドギターを弾きまくっていた。ここでもそのマナーは踏襲され、15分は演っていただろうか、最後は匂い立つようにブルージーな、熱い幕引きとなった。
70代直前といっても、枯れた味わいとは無縁。前々作と前作ではジャズにアプローチして、年相応といえば年相応な世界を拡げていたが、やはり「侘び寂び」よりも「艶」が先に立つ人である。自然体であれだけ伸びやかな声を出せるのは並大抵のことではない。
終わってみれば、最新作から5曲、『Silk Degrees』からは6曲を演奏したことになる。もう少し他のアルバムからの曲も聴きたかった気がするが、これはこれで充分に粋なショウだった。
それにしても、晩秋が似合うなんていうのは勝手な思い込みだったな。季節がいつであれ、この人には関係ないのだろう。いつか、真夏の夕方、野外で風に吹かれながら聴いてみたい。
TEXT:大内幹男
◎イベント情報
2013年11月20日(水)
@尼崎・あましんアルカイックホール
Boz Scaggs/ボズ・スキャッグス