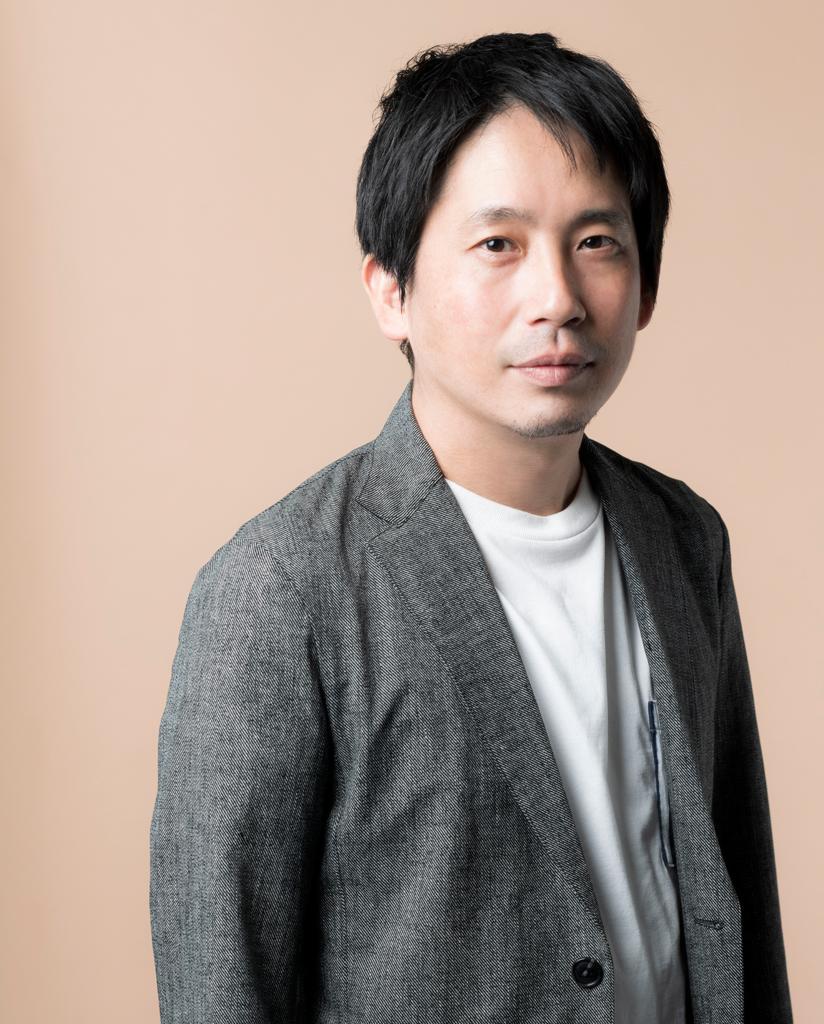
都内にカウンセリングルームを開設する臨床心理士であり、前作『居るのはつらいよ』が大佛次郎論壇賞を受賞した東畑開人さん。このエッセイ集では、政治、経済、新型コロナウイルスのような「大きすぎる物語」に「吹き飛ばされてしまった小さな物語」を探して、そこにある「心」を見つめている。
昨年4月、東畑さんが教えている大学がコロナで封鎖されると、学生からの履修登録の問い合わせメールが急増した。
「学生が大学に集まっていたときは僕に聞かなくてもみんな履修登録ができていた。見えないヘルプが飛び交って、互いに助けられていたんです」
コロナで失われた場の意味や、コロナ以前の社会の姿が見えてくる。
東畑さんは河合隼雄さんの本をきっかけに心理学の道に進んだ。しかし2000年代以降、経済優先の流れが強まり、会社も個人も生き残りに必死になるにつれ、河合さんが取り組んできた、物語の力を信じる心理学は退潮していった。
「物語は何の役に立つのかと言われ居場所が小さくなりました。今はコロナで人が集まって物語を共有することがしにくくなり、自分の小さい世界でどう生きていくかを一人で考えがちです。そういう時代にこそ心についての物語が必要な気がしています」
『心はどこへ消えた?』(文藝春秋 1650円※税込み)は「週刊文春」の連載が基になっている。深い話を楽しく読ませてくれる文章も大きな魅力だが、スイスイ書いたわけではない。
「本当につらかった。書いていて、次の文章が見つからないんです。ちょっとずつ進んでいくんですけど、素材が出揃うまでに苦しさがある。こんなものでいいのかと自分を責める声が強い人間なので大変でした」
書くことはつらいけれど、癒やしでもある。
「何かを言葉の形にすることが持つ癒やしというか、心が整う。ワッと書き散らかすのではなく、時間をかけて文章という形にしていくから、自分なりに一つのことをちゃんと考えた感じがするし、ちょっとずつ前に進んでいる気がするんです」
































