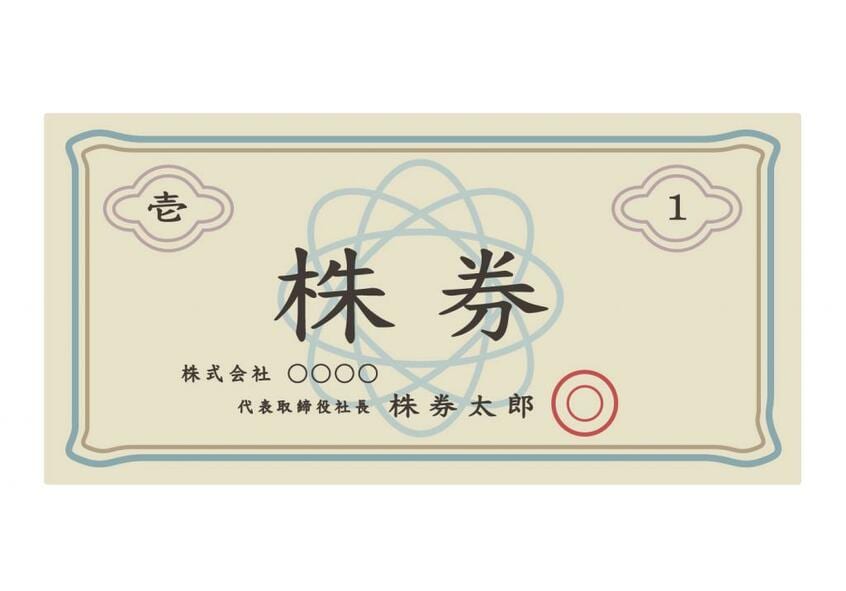
コロナをきっかけに、相続トラブルに発展したケースはほかにもある。
全国でも高齢化率が高い北九州市で、相続・遺言・後見業務にあたり、近著に『図解でわかる 改正民法・不動産登記法の基本』(日本実業出版社)などがある司法書士のぞみ総合事務所代表の岡信太郎さんは、「コロナによって、約2年間、人流や話し合いが途絶えたことで、今になって相続人が増えている、あるいは病気が進んで相続人の意思確認が取れなくなり困るケースが増えている」と話す。
九州地方で暮らす70代男性Cさんの例を挙げよう。Cさんは3兄弟の次男で、長男、三男とは仲が良く、定年後も交流してきた。そんな中、長男が1年前に亡くなる。長男には妻子がいなかったため、Cさんと三男が法定相続人となり、2人で長男の財産(持ち家と預金2千万円)を分け合うことになった。
ところがコロナ禍により遺産分割協議は延期に。Cさんは「コロナが落ち着いてから再開しよう」と考えていたが、その間に三男が大動脈瘤破裂により突然死してしまう。これにより「数次相続」が発生し、三男の妻と子ども2人(甥姪)に、長男の遺産を分け与えることになってしまった。
「数次相続の場合、自分とは血縁関係のない『兄弟姉妹の配偶者』も相続人となるため、『どうして故人と関係のない者にまで遺産を渡さなければならないのか』とトラブルになるケースが少なくありません。また、相続人が増えることで、必要な手続きや費用が予想外に膨らんでしまい、不公平感を抱く人も多いですね」(岡さん)
関西地方で暮らす60代女性のDさんは、遺産相続が難航したことが心的負担となり、うつ病になってしまった。
Dさんは、親元を離れて夫と子ども2人と暮らしていた。しかし昨年末に、福岡で一人暮らしをしていた父親が死去。母親は持病があり入院していたため、一人娘のDさんが遺産整理を進めることになった。
会社役員だった父親は、不動産、預貯金、株などの有価証券と、複数の財産を所有していたが、遺言は残されていなかった。そこで法定相続人である母親と遺産分割協議を始めようとしたが、その矢先、コロナにより病院が面会謝絶となってしまったのだ。





































