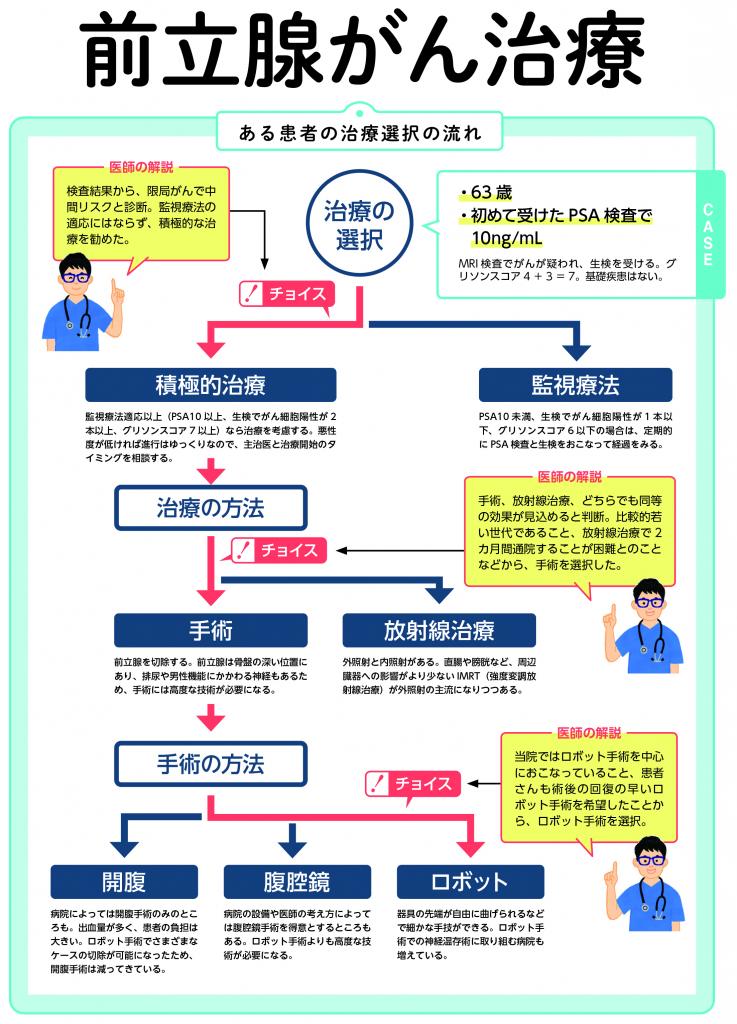
■合併症、治療の受けやすさ、再発時の治療を考えて選択
前立腺がんの治療は、ほかの多くのがん治療と異なり、初期の段階であれば手術と放射線治療の成績が同じで、治療後の生存期間に大きな差がないことが特徴だ。「初期」とは、がんが前立腺内にとどまり(限局がん)、悪性度が低い(がんの悪性度を示すグリソンスコアが6以下)場合を指す。
さらに、放射線治療には、放射線をからだの外から当てる「外照射」、前立腺の中に放射線を放出する物質(線源)を埋め込む「内照射」がある。照射する放射線の種類も、X線、重粒子線など、複数ある。
がん治療において、このように選択肢が多いことは心強い。しかし、治療法を決定する際の迷いのもとともなる。何を判断材料とすればいいのだろうか。
まず、それぞれの手技を比べてみよう。
■手術と放射線治療 それぞれの特徴を検討
手術はロボット手術が主流になっている。腹部に4~6カ所穴を開けてそこから器具を挿入し、前立腺を切除する。出血量は少量で、からだへの負担は少ない。腹腔鏡手術の方法はロボット手術と同じで、いずれも全身麻酔下でおこない、入院期間は7~14日程度だ。
外照射は皮膚の切開もなく入院が不要だが、通常、約2カ月の通院が必要になる。内照射は小線源を埋め込むための処置が必要になる。3~4日の入院で、腰椎麻酔での処置が一般的だ。
治療の合併症はどうだろうか。
手術では前立腺の周囲に存在する、排尿や男性機能にかかわる神経を傷つけるリスクがあり、ある程度の尿漏れや勃起障害が起こる。しかし神経温存手術の発達で早期に回復するようになり、個人差があるが、尿漏れは1年後には約9割が、勃起障害は5~7割が回復するという。
一方、外照射では、治療中から治療後数カ月にかけて、勃起障害、頻尿や排尿困難などが起こる。また、治療後数年たってから膀胱炎や、直腸、膀胱からの出血などが起こる「晩期合併症」のリスクがあるのも特徴だ。




































