田中:日本の姿勢については「対米従属」が如実に表れていると思います。特に戦時体制については、米国の顔色をうかがうばかりで自分で態度を決められない。「今回のロシアの動きが何らかの形で中国に波及する」「軍備を増強しないと日本が危険だ」など、「こうなっちゃうんじゃないか」と怖がって対策を練るばかりではなく、この状況を自分たちがどう変えられるのかという発想が本当は必要。停戦の仲介はその第一歩です。まず停戦をしてその後、どうしていくかを考える。
私は戦争を起こしたい人たちや、戦争を起こそうという動きそのものは、なくなることはないと思います。南北朝鮮を見ても、完全に戦争が「終わる」ということはない。だからこそ、私たちが戦争を起こさないためには「停戦状態をつなげていく」しかないんです。
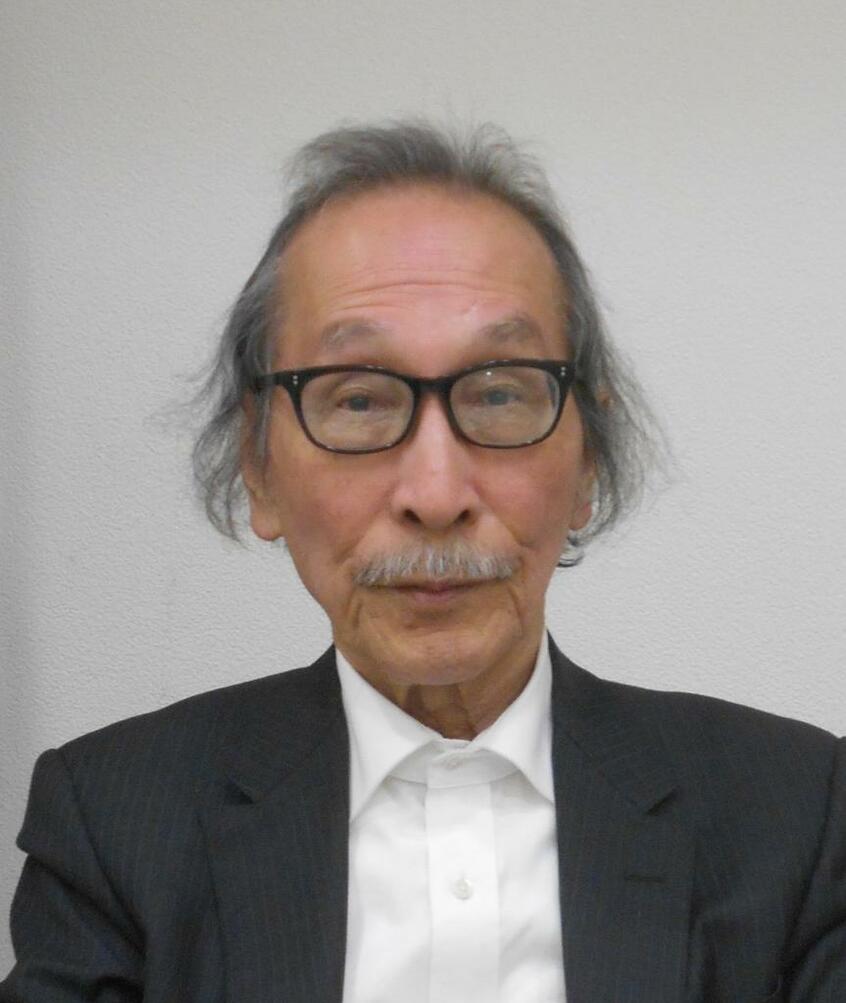
■声明に対し批判の声も
田中:2回目の声明は学者だけでなく、作家やジャーナリストらも賛同者として署名した。一方で、「停戦や撤退はウクライナにではなく侵略したロシアに言うべきだ」「ロシアにも言い分があるという考え方はおかしい」「停戦を日本が仲介したところで『合意後の維持』が担保できない」といった若手の研究者からの批判もあった。
和田:私たちは「ロシアにも言い分があるんだから戦争して当然だ」と言っているわけでは決してありません。ただし、ロシアが戦争を起こすにあたって「ロシアにはロシアの言い分がある」のも事実です。停戦して何らかの妥協によって戦争を終えるとすれば、ロシアの主張をある程度考慮することもやむを得ない。公正な仲裁者が双方の話をよく聞き、妥協点を見つけることが必要です。仲裁に立つのは大変なことです。「停戦の後のこと」にも責任を持たなきゃならないのですから。
停戦協定を結んだ後には世界中の主要な国を集めて会議を開き、停戦合意を認めたうえで、ウクライナの安全保障と復興、戦争犯罪の処理への協力を相談しなければなりません。世界中の国が協力しなければ、より良い平和の方向に持っていくことはできないと思います。


































