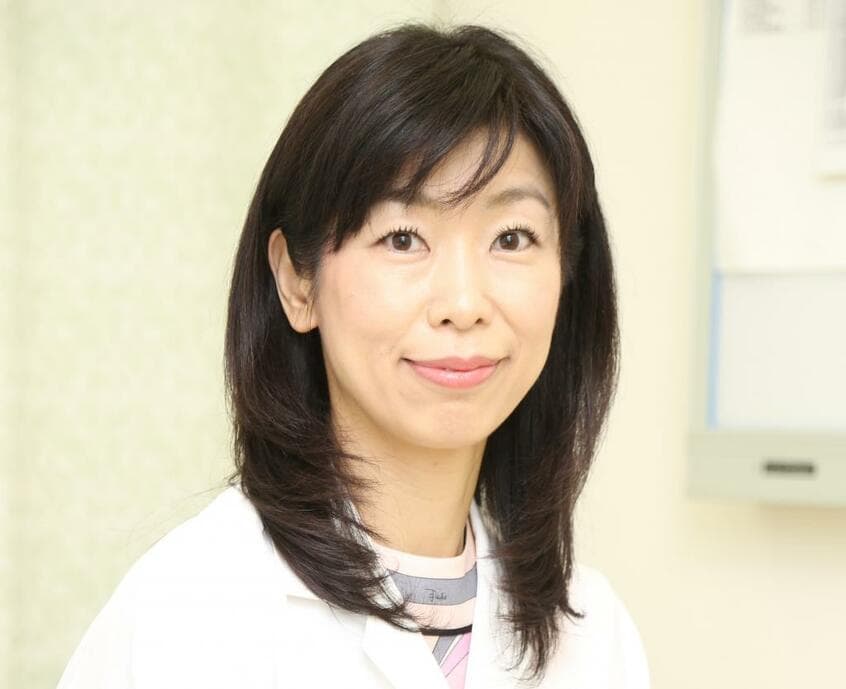
「巡りの悪さによる疲れ」の対策とは
このタイプの疲れは、「血」と「水」の巡りが悪くなり起こるもので、運動不足の人やデスクワークの人、入浴習慣がない人に多く見られます。基本的な対策は、体を動かすこと。特にウォーキングやジョギングなどの脚を使う運動がおすすめです。“第二の心臓”ともいわれるふくらはぎがポンプ役として働き、脚から心臓に向かって血液を戻してくれるので、むくみの予防・改善、全身の血行もよくしてくれます。
また、「血」や「水」の巡りをよくするには、体を冷やさないことも大切です。運動で筋肉をつけることは、冷えにくい体づくりにとっても重要なことといえます。
「加齢に伴う疲れ」の対策とは
漢方の考え方では女性は体のピークを過ぎた35歳以降は、それ以前と比べると「気」が少なくなるため、疲れやすくなっていきます。「気」が少なくなると徐々に「血」も少なくなっていきます。新陳代謝が低下することで冷えやすくなり、冷えが疲れを助長するケースも見られます。
「気」は睡眠によって補われますが、眠るにもエネルギーが必要。加齢に伴い睡眠時間は短くなり、睡眠の質も悪くなります。昼寝などで効果的に「気」をチャージしましょう。日常生活で起こる様々な“変化”によっても「気」は消耗します。季節の変わり目や非日常的なイベントなどでは「気」をつかい過ぎないことも大切です。
「虚弱状態による疲れ」の対策とは
30代や40代の人が、疲れがとれないことを年齢のせいにするのは早過ぎます。年齢よりはむしろ、生活習慣により「気」をすり減らしてしまったことが原因。本来は虚弱体質ではないのに、「気」がすり減ることで“虚弱体質のような状態”に陥っているのです。虚弱状態による疲れを放置すると、疲れ過ぎて体が動かなくなったり、気力がなくなって年齢以上に老け込んだりしてしまうこともあります。
この疲れの症状は、食欲がなくなったり、下痢や便秘になったりするなど「消化器」に現れる人と、咳や鼻水、かぜをひきやすいなど「呼吸器」に現れる人がいます。症状に応じた対策を施しましょう。
前編<<疲れが取れないのは「貧血」が原因のことも 漢方専門医に聞く女性の「疲れ対策」>>から続く
監修/木村容子(きむら・ようこ)先生
東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長、教授。お茶の水女子大学卒業後、中央官庁入省。英国オックスフォード大学大学院留学中に漢方と出会い、帰国後退職して東海大学医学部に学士入学。2002年より東京女子医科大学附属東洋医学研究所に勤務。医学博士。日本内科学会認定医。日本東洋医学会理事、専門医、指導医。著書に『女40歳からの「不調」を感じたら読む本』(静山社文庫)、『太りやすく、痩せにくくなったら読む本』(だいわ文庫)、『ストレス不調を自分でスッキリ解消する本』(さくら舎)他。






































