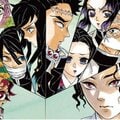「ランキングは純資産総額で順位付けしてありますが、これらの売れ筋が必ずしも有望とは限りません。売れている理由は、依然、日本では投資でお金を増やすことに抵抗を感じる人が多いからでしょう。SDGs系投信は社会貢献にもなるという大義名分が、背中を押しやすい」
金融機関の窓口で複数の投信を薦められ、「社会貢献になるし、実際に売れているし……」と判断するパターンが多い様子。実際、ランキング上位10本中6本は対面営業に注力する大手金融機関の専用ファンドだ。
肝心の実績はどうか。SDGs系投信は現状、米国株の比率が高めだ。それぞれの投信のリターンを米国株の平均的な動きを表すS&P500投信(直近1年で40%台)と比較すると、劣るものが多い。一概に米国株と比較するのは乱暴かもしれないが、しっかり上回っている投信は10本以下である。
一方、ランキングの中で10年以上の運用実績がある投信が2本ある。26位の朝日ライフの投信は10年で145%、28位の野村の投信は同240%。
「SRI(社会的責任投資)の観点で銘柄を選ぶ投信です。SRIは欧州で用いられてきた手法で、たばこやギャンブルなどキリスト教の教えに反する分野に関わる企業を除外したのが発祥といわれます。SDGsやESGを冠する投信と運用の趣旨はほとんど変わりません」
こうした歴史的な背景から、欧州系の運用会社はSDGs系投信の運用に関して一日の長がある。米国系や国内系は熟達しているとは言いがたい。たとえば日産自動車はゴーン騒動で知られるようにガバナンス=Gの評価が低いというが、国内運用のESG投信にはなぜか組み込まれているものもある。
■コスト年率1.7%超
資産運用という観点から、さらにプロの意見を聞こう。ファイナンシャルプランナーの藤川太さんは語る。
「SDGsなどへの取り組みがうまくいって業績に反映されるまで長い時間がかかります。長期投資だからこそ、この手の投信はコスト面で分が悪い」