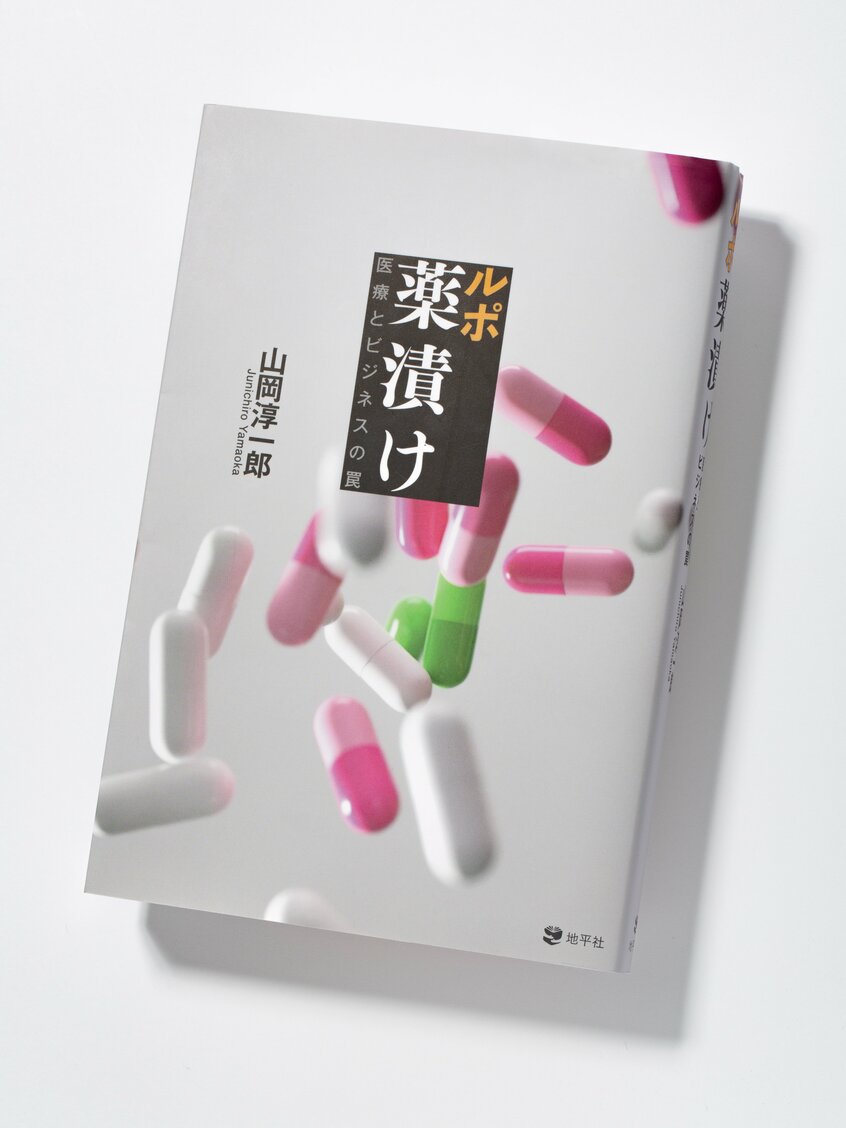
「社会的に『うつ病』への認知が広まって、グレーゾーンにいる人たちが休みやすくなったなど良い面もあります。でもいっぽうで向精神薬に簡単にアクセスできるようになり、そこから薬にのみ込まれてしまう人も増えていった」
激務からうつ病を発症し、向精神薬を大量に処方された末に命を絶った24歳の看護師の遺族や、オーバードーズを繰り返す娘との格闘を語る母など、当事者たちの証言に胸をえぐられる。専門家にも取材を重ね、なぜ薬が増えてしまうのか、減薬や断薬が難しい理由も解き明かした。
「抗うつ薬を飲むと、本来の脳の平衡が崩れた状態でバランスが保たれるようになる。そこで薬をやめるとおもりを外した状態になり、バランスが崩れて調子が悪くなってしまう。そのバランスをうまく調整して薬と付き合うことが理想ですが、医師によっては『薬が効いていない』と判断し、さらに多く薬を出してしまうことがあるのです」
認知症の薬の是非、さらには発達障害と診断された6歳以下の子どもにも「おとなしくさせるために」薬が処方されている現状にも斬り込んだ。
「薬を飲むかどうかは本来、本人が判断して決めるものです。しかし精神疾患や認知症のある人、幼い子どもに自己決定権があるかどうか。取材しながらしみじみ考えました」
「薬漬け」から逃れるためには結局、患者の状態をしっかり見極めてくれるいい医者に出会うことがすべて、と山岡さん。
「病は人と人の関わり合いのなかで治していくもの。これがやはり一番、大事なことだと思います」
(フリーランス記者・中村千晶)
※AERA 2025年8月25日号
こちらの記事もおすすめ 滝川クリステル「表紙を見ただけで“やってみたい”の気持ちに」 童話「赤ずきん」再解釈本








































