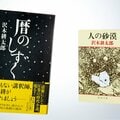私が大学生の時、共同通信を受けたのは、横川和夫さんという共同の記者が書いた『荒廃のカルテ』というルポルタージュを読んだからだった。1983年におきた女子大生暴行殺人事件の犯人である少年の成育歴を追ったもので、なぜ人が人を殺すのか? それがなぜ少年なのか、ということを追ったルポで、興奮した。大学生だった私はこういうものを将来書けるようになりたい。そう最終面接で息せき切って話す私を、しかし、共同の役員は静かにこう制したのだった。
「横川君のやった仕事は共同の中では例外的な仕事。通信社の記者というのは、もっと地味な黒子なんだよ。地方紙のための記事を配信するのだけれど、その記事は署名でもない。しかも記事を掲載するか否かは、地方紙の判断によるんだよ。通信社はあくまでも黒子。君のような性格の人は、出版社とか他のところに行ったほうがいい」
そうあっさり引導を渡された。当時は、その役員が言うことの意味がまったくわからなかったが、今では、よくぞ正直に通信社の存在意義をまだ何もわからない学生に話をしてくれた、と感謝をしている。
こんな大昔のことを思い出したのは、今年の3月14日に共同通信が対価とひきかえに共同の記事をグーグルの生成AIに提供する契約を結んだ、という報道に接したからだった。
共同はルビコンを渡ったのか、そう衝撃をうけた。
新聞社のサイトを訪れる人が激減している
と、言われても一般の読者の方には、その意味はすぐにわからないと思う。共同通信の中の人や地方紙の人たちも、これがいかに衝撃的なことかわかっている人は案外すくないかもしれない。
この連載で何回か、生成AIとジャーナリズムの関係について書いているが、そこには深刻な利益相反があると、私は考えている。
これを確かめるには、ニューヨーク・タイムズがOpenAIを提訴したその訴状を読むのが分かりやすい。
OpenAIは生成AIのサービスChatGPTを開発、運営している会社だ。タイムズがなぜOpenAIを訴えたかというと、ChatGPTは、タイムズの有料記事を出典を示さずに吐き出したり、また、タイムズが報道していないことを、架空の記事をつくって報道したと答えたりすることを、タイムズが確認をしたからだ。これらがタイムズの著作権を侵害し、利益を損なっていると提訴したのだ。