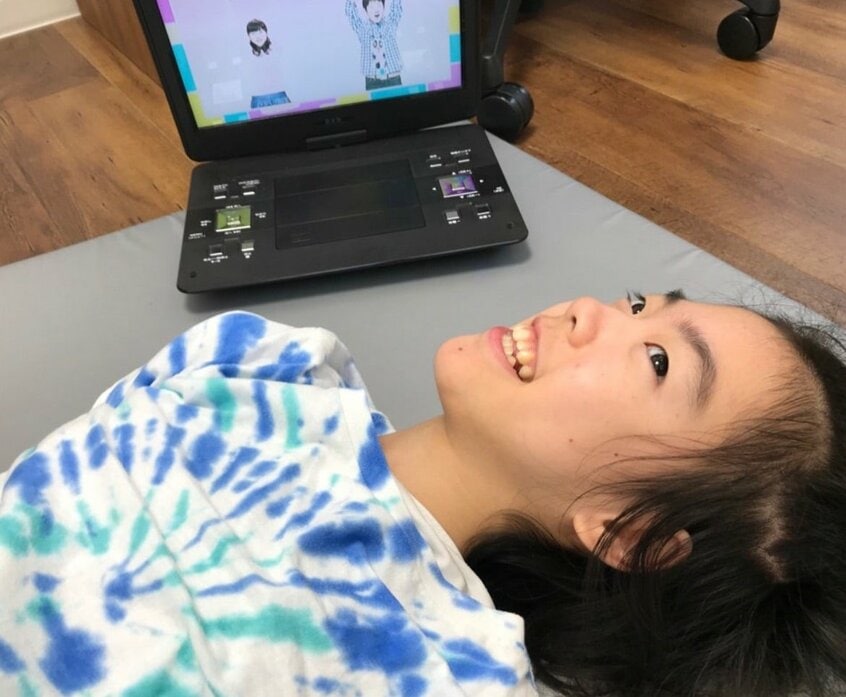
「インクルーシブ」「インクルージョン」という言葉を知っていますか? 障害や多様性を排除するのではなく、「共生していく」という意味です。自身も障害のある子どもを持ち、滞在先のハワイでインクルーシブ教育に出合った江利川ちひろさんが、インクルーシブ教育の大切さや日本での課題を伝えます。
* * *
7月末に、重症心身障害児の長女の療育手帳(知的障害者に交付される手帳)の更新がありました。18歳を過ぎて今年3月に特別支援学校を卒業し、私が住んでいる自治体では、今後は再判定を省略することになるので、今回が最後の更新です。今回は療育手帳について書いてみようと思います。
18歳以上になったことを実感
更新手続き当日。長女は地元の療育センターで発達検査を受けました。このセンターは中央に受付があり、左右に療育センターと児童相談所が分かれています。療育手帳の取得は本来、児童相談所の管轄ですが、18歳のお誕生日が過ぎると対象外となり、障害者更生相談所の役割を兼ねる療育センターで検査を受けるのです(自治体により、障害者更生相談所の場所は違いがあります)。
すでに何度か児童相談所で更新をしていたので、私も「療育手帳=児童相談所」というイメージが強く残っており、改めて18歳以上になったことを実感しました。
そしてこの療育センターは、0歳から6歳までリハビリに通い、5歳から人工呼吸器が必要になった12歳まで、在宅介護をしている家族の休息などを目的に短期間入院する「レスパイト」で利用していた施設です。受付や廊下も当時とほぼ変わりなく、とても懐かしく思いました。
今回はもう19歳ということもあり、大々的な検査よりも日常の聞き取りの方が多かったように思います。長女の精神年齢は1歳程度とされているので、タオル地のボールを握ることができるかや、鏡に写った自分に興味を持つかなど、赤ちゃんに対する遊びのような内容です。長女は「ママ」という発語があるので精神年齢が少し高めに出るようですが、実際の発達検査の内容はほぼできません。今はできてもできなくても長女は長女であり、一喜一憂することはありませんが、最初にこの検査を受けたときには、長女よりも私が緊張し、ほんの少しでも長女ができることをアピールしていました。今思うと、もしかすると長女は私の感情を敏感に感じ取り、逆効果だったかもしれませんね。





































