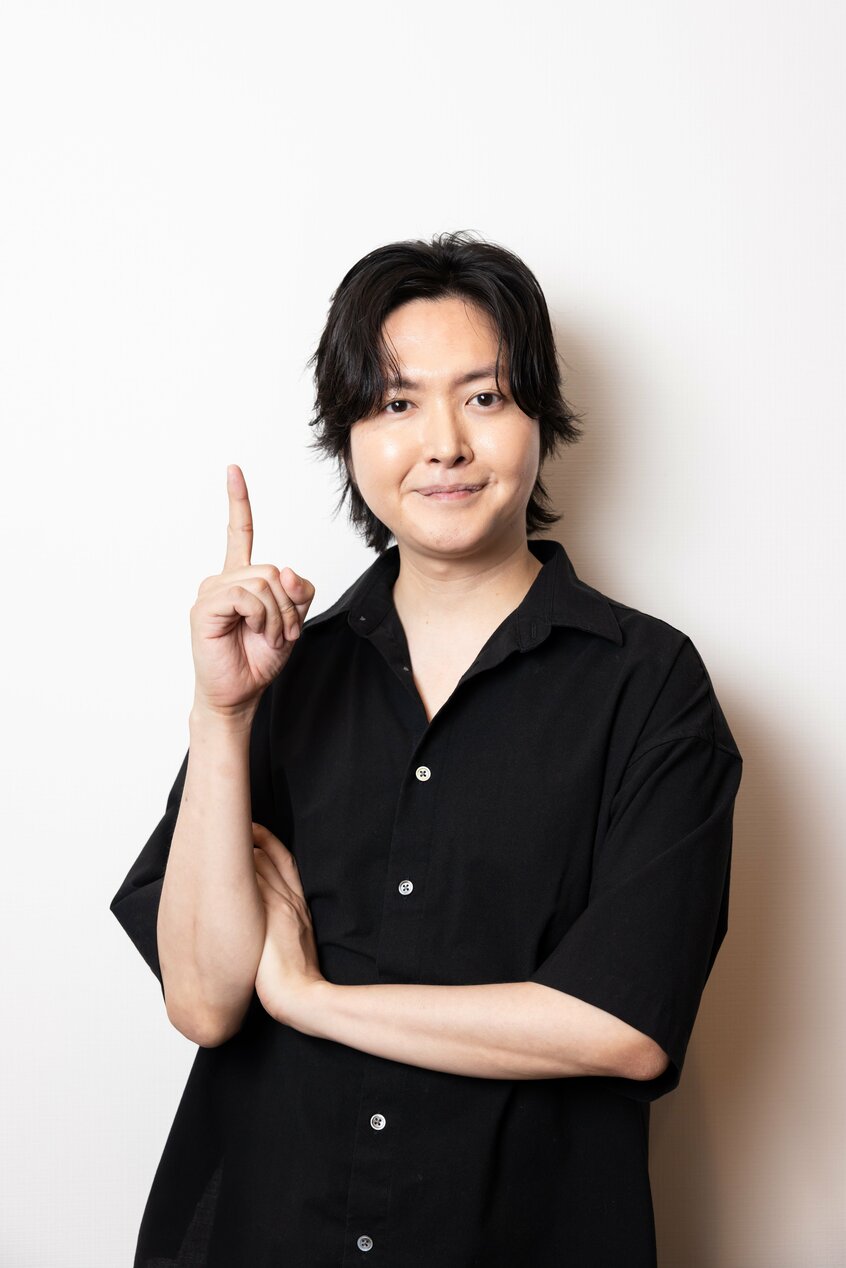
イタリア、フランス、ベトナム、中国……人気料理研究家のリュウジ氏は10代の時、世界一周旅行に行った経験がある。そこで得た「料理理論の気づき」とは? 自身の料理哲学を語りつくした最新刊『孤独の台所』(朝日新聞出版)より、一部を抜粋してお届けする。
* * *
世界一周旅行での食体験は、すぐに役に立つことはありませんでした。
でも10年経ち15年経ち、そして料理研究家になった今、すごく良い経験として気づきをもたらしてくれます。
どうしてあの料理はおいしく感じなかったのか、どうしてあの料理はおいしく感じたのか……理由があとからわかってきて、言葉にできるようになってきたのです。
世界一周から戻ってきて最初に感じたのは、醤油のありがたさです。
これは日本の味が恋しくなったとかいう単純な話ではなくて、料理の理論として意味がある発見でした。
実は、旅行に出発する前は、醤油ってそんなに好きではなかったんです。
刺身につけるのはいいけれど、そんなにうまいものかなと思いながら口に運んでいました。鮮度の良い刺身ならカルパッチョにしてもいいし、なんならオリーブオイルと塩で野菜とあえてもうまいじゃん、と。醤油が必須だとはまったく感じなかった。
でも帰国してから、醤油はうま味が豊富な最高の調味料なんだと気づきました。こんなに良い調味料をなんで俺は邪険に扱っていたんだろう。「ごめんね、醤油」と思ったわけです。
「コク」の洋食、「うま味」の和食
フランス料理が典型ですが、西洋料理はメインの具材がうま味を担当します。それにバターや生クリームを軸とした油脂分たっぷりのソースを足すことでご馳走にする、という発想が強いんです。どちらかというと、うま味よりコクを大切にしている文化なんですよね。
逆に和食は、うま味のある素材に、さらに出汁や調味料のうま味を掛け合わせていくことで、油脂分が少なくても満足できる料理を目指しています。
醤油もうまいし、味噌は出汁をひかずにお湯に溶かすだけで汁物として完成してしまうくらい、おいしい調味料です。具材、出汁、調味料と異なるうま味を何重にも組み合わせるのが和食の特徴なわけです。
出汁も、昆布の「グルタミン酸」とかつお節の「イノシン酸」の相乗効果で強いうま味を持たせれば、よりうまくなって当たり前です。
(リュウジ・著『孤独の台所』では、世界一周での食体験、料理人としての挫折を通じて気づいた「家庭料理の本質」について語っている)







































