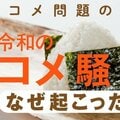「転売ヤー」はコストをかけて米を保管するか
米の高騰の原因の一つとして、昨年の新米の時期に投機目的の「転売ヤー」が農家を訪れ、米を買いあさったという報道もあった。しかし、早場米の産地、千葉県匝瑳(そうさ)市の栄営農組合の伊藤秀雄顧問は、転売ヤー説に否定的だ。
通常、収穫した米は、玄米の状態で、室温14度に管理された倉庫で保管される。転売ヤーがコストのかかる低温倉庫を借りてまで米を保管するとは思えないという。
「玄米は15度を超えると、虫が湧く。そうしたら商品にはならない。通常の倉庫であれば、今年2月下旬が保管の限界です。それを過ぎても、米が出てきた形跡はなく、米価は下がらなかった」(伊藤さん)
JA悪玉論は「明らかな間違い」と専門家
SNSでは、「米高騰の元凶はJA」という声や、「JAこそ転売ヤー」といった声までが散見される。農家から米を買い取る際、JAが価格をつり上げている、というのだ。確かに、米の卸売(相対取引)価格は2023年産米で、60キロ1万5315円だったが、24年産米は同2万3715円と、大きく上昇している。
だが、JA悪玉論は「明らかな間違い」だと東京大学大学院・鈴木宣弘特任教授は指摘する。
「米の価格を引き上げるどころか、JAは他の民間業者に買い負けて、計画していた量を集められず、困っているのが実情です」(鈴木特任教授)
1942年から95年まで続いた食糧管理制度のもとでは、JAは米のほぼ全量を集荷していた。だが、同制度が廃止され、米の流通が自由化されると、JAの集荷率は下がり、「昨年はついに3割弱に低下した」(同)。前出の栄営農組合の場合、JAを通して出荷する米は全体の約1割に過ぎず、大半を民間業者に売り渡している。
「客観的に見て、JAに米の価格をつり上げる力はもうありません」(同)
米が足りないから高値で買い集める
では、高値で米を買い取っている民間の集荷業者が米価高騰の原因なのか。
「それは原因と結果の関係が逆です。米が足りていないため、集荷業者は高値で米を買い集めざるを得ない状況にあるのです」(同)
米不足というシンプルな問題が、なぜここまでこじれるのか。
「農水省のメンツの問題としか思えません。『自分たちが行ってきた米の生産量の調整にミスはない。であれば、米騒動の原因は他にあるはずだ』と。メンツのために流通業者叩きをしているようにみえる」
米問題の原因が究明されず、解決にも結びつかない裏には、「農水省に由来するいくつもの理由がある」と鈴木特任教授は言う。
次回は、なぜ、米不足が統計上は米不足と認識されないのか、そのカラクリを解説する。
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 【真相ルポ】「米が足りない」現場の訴えを農水省は握りつぶした 発端は2年前の「猛暑」 1等米がわずか4.9%に